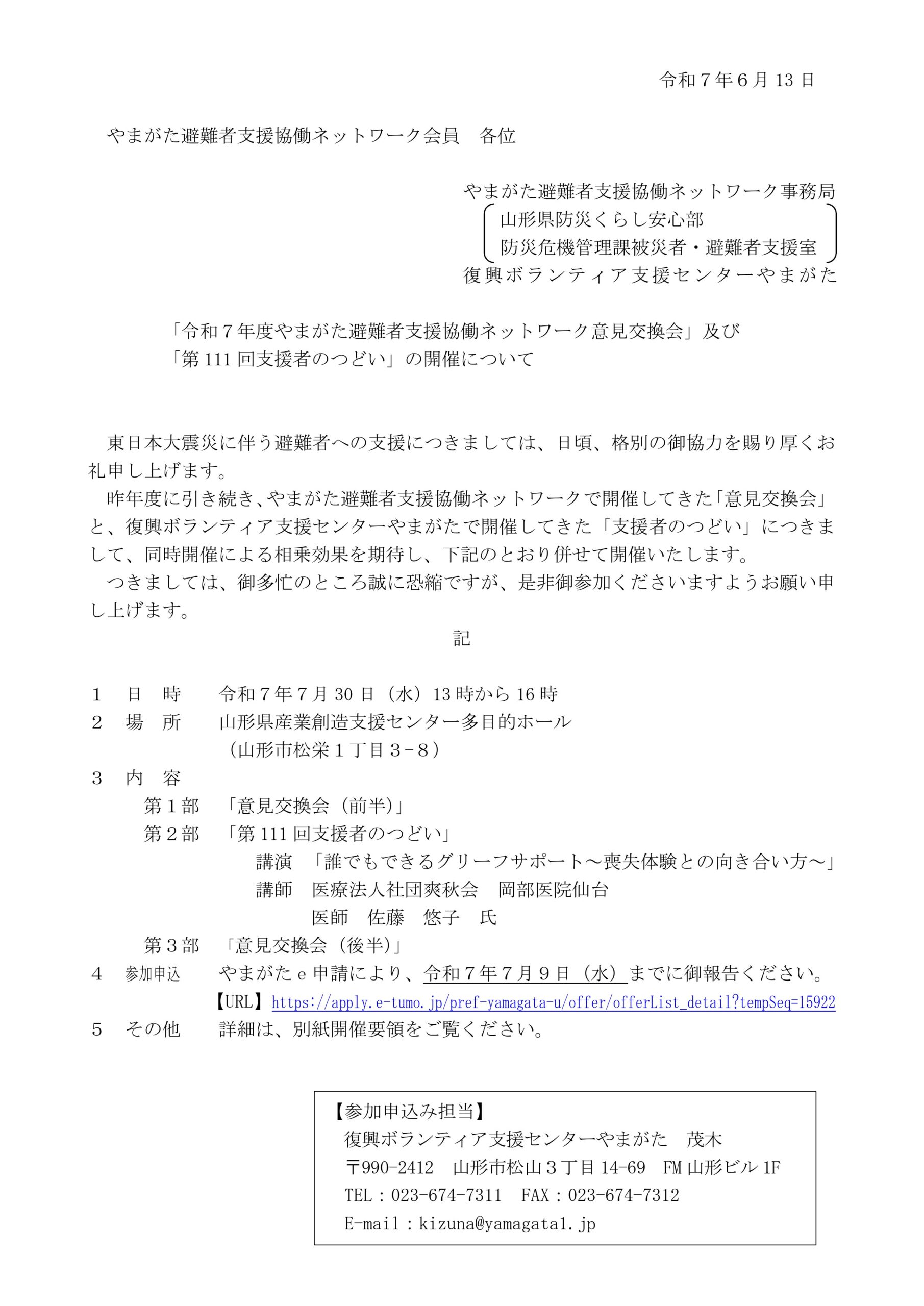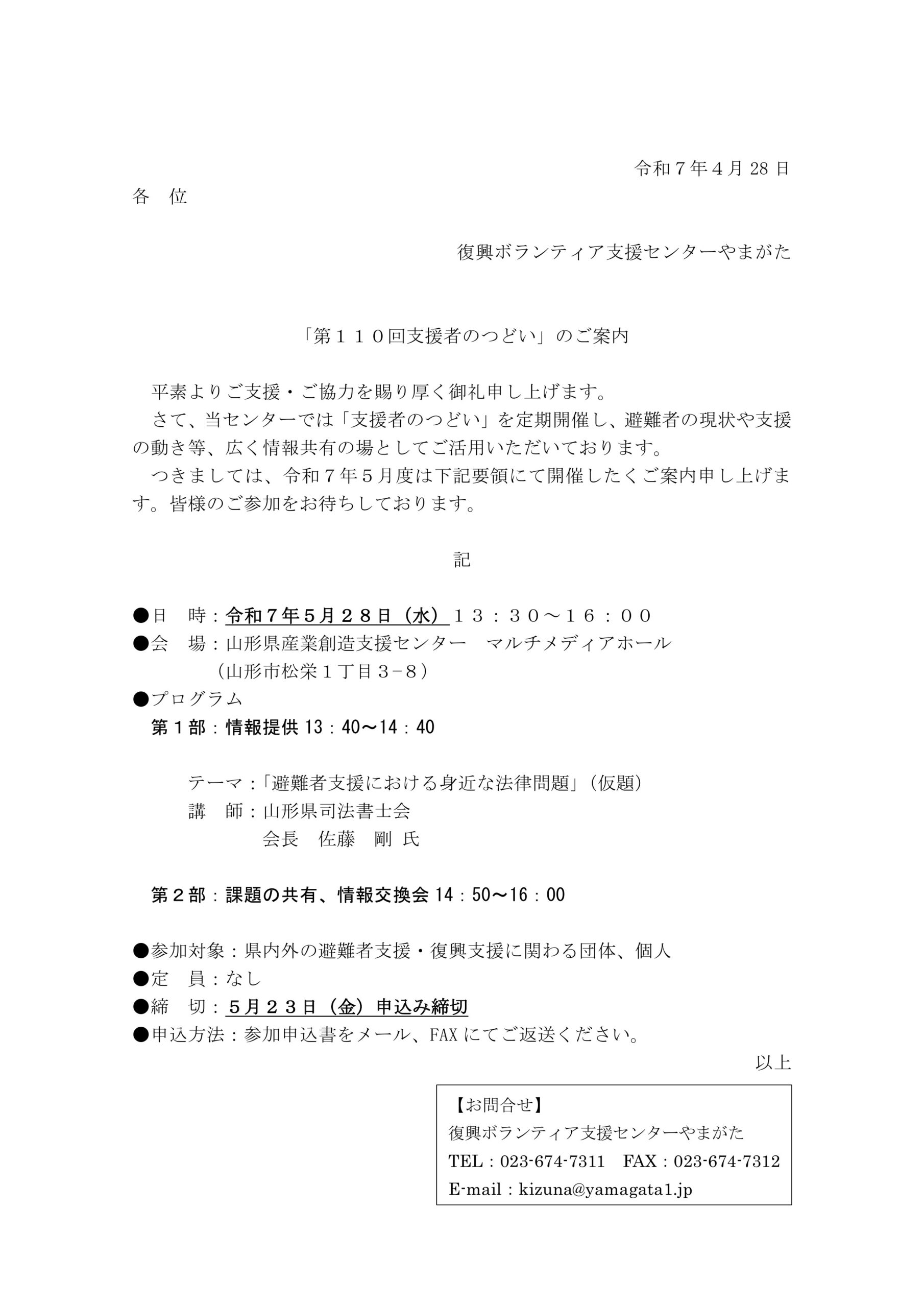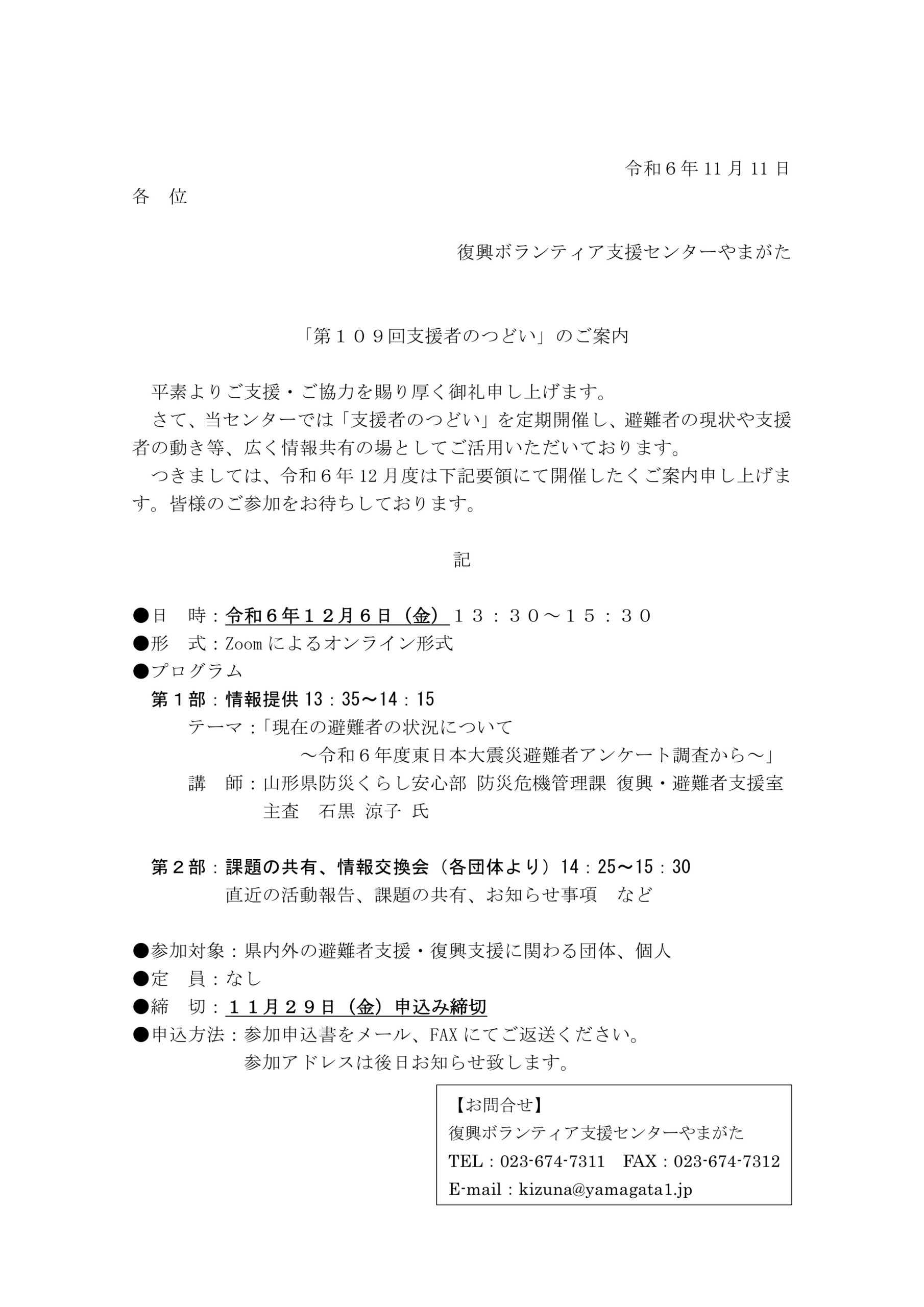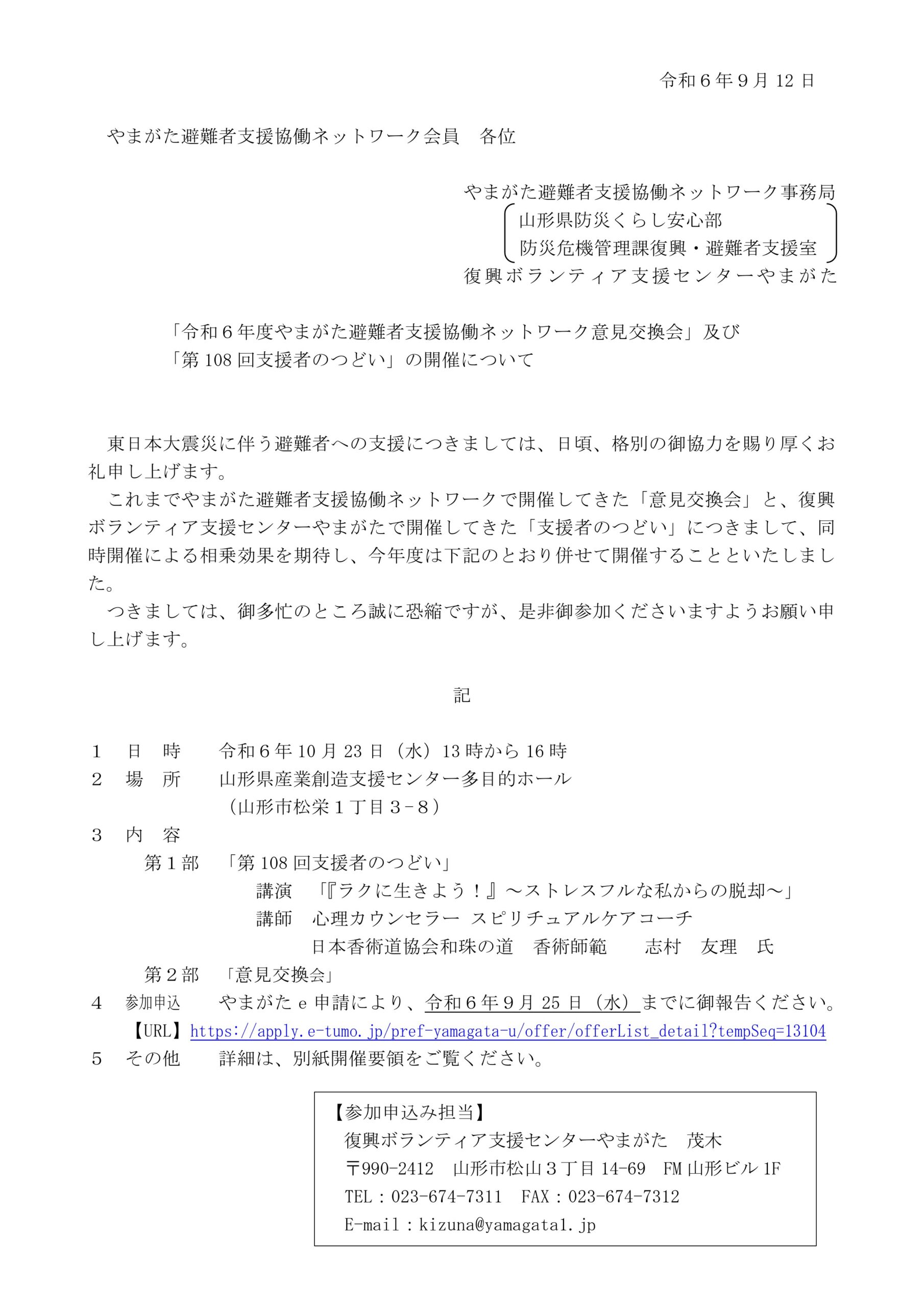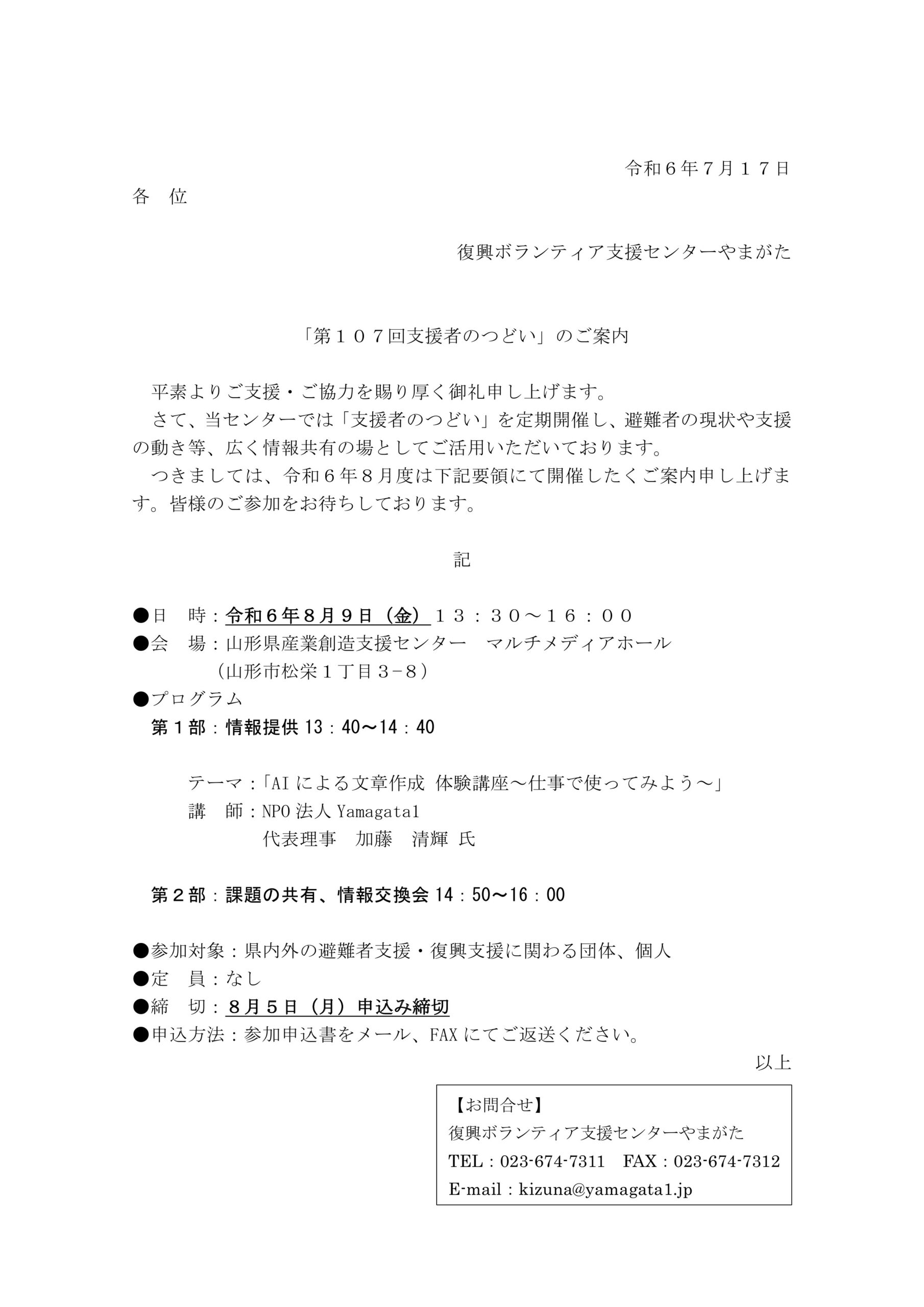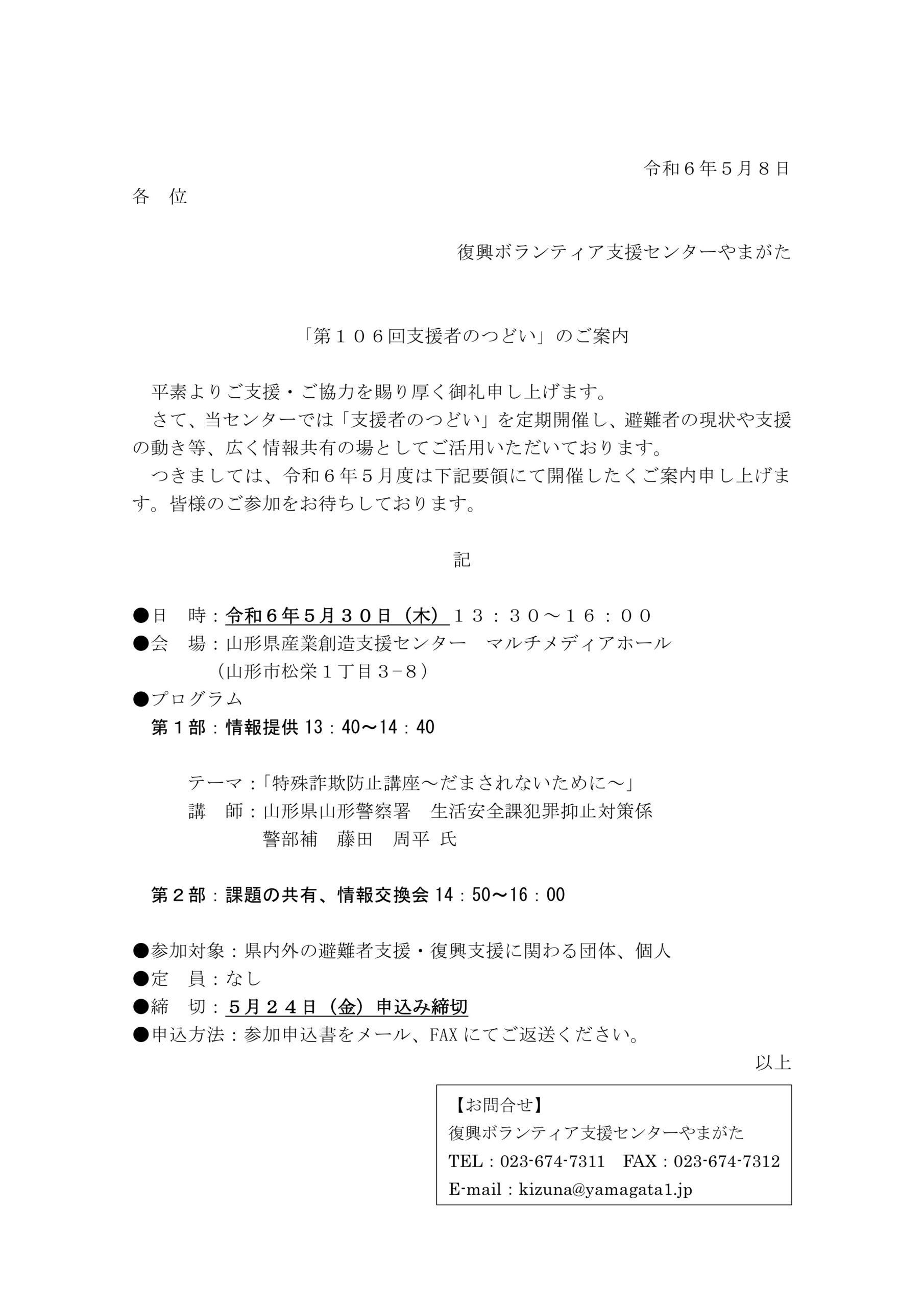å¹³æ29å¹´9æ29æ¥ï¼éï¼ãå¯æ²³æ±å¸æè¡äº¤æµãã©ã¶ãä¼å ´ã«ã第71å ãæ¯æ´è
ã®ã¤ã©ãããéå¬ãã¾ããã話é¡ã¨ãªã£ãæ¦è¦ãåºãçæ§ã«ãä¼ããã¾ãã
ãåå é ãã¾ããçæ§ããããã¨ããããã¾ããã
ãªãã1é¨ã¨2é¨ã«åãã¦æ²è¼ãã¦ãã¾ãã
ï¼åå è
ï¼
ä¸éæ¯æ´å£ä½ãï¼å£ä½
æ¯åæ¯æ´å£ä½ãï¼å£ä½
ã³ãã¥ããã£æ¯æ´å£ä½ãï¼å£ä½
山形å¸ç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼
å¯æ²³æ±å¸ç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼
鶴岡å¸ç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼
é
ç°å¸ç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼
天童å¸ç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼
山形ç社ä¼ç¦ç¥åè°ä¼
山形å¸é¿é£è
交æµæ¯æ´ã»ã³ã¿ã¼
山形ç復èã»é¿é£è
æ¯æ´å®¤
åå è
æ°ï¼18åï¼13å£ä½ï¼ããã¹ã¿ããï¼4åããè¨22å
â 第1é¨ãæ¯æ´æ´»åã«é¢ããæ
å ±æä¾ã質çå¿ç
ããããããé¿é£æ示解é¤ããéããªãåå¹´ï½æµªæ±çºã»åç¸é¦¬å¸ã®ä»ã®æ®ããï½ã
ãããããããæä¾è
ï¼å
é¿é£è
ï¼åç¸é¦¬å¸å¨ä½è
ã»éç½å¾ã¯åç¸é¦¬å¸ããäºæ¬æ¾å¸ã«é¿é£ãããã®å¾æ¯ã®å®å®¶ããã山形çå
ã«3æ15æ¥ã«é¿é£ããã社ä¼ç¦ç¥åè°ä¼ã®ç¸è«å¡ã3å¹´ãã¦ãããç¸è«å¡æ代ã¯è¢«ç½ä¸çããã®é¿é£è
ã«ã便ããçºè¡ãã交æµä¼ãéå¬ãã¦åå è
ã¨å©ãåãæ¯ãåã£ãã
ã»å¸°éã®ãã£ããã¯ç¶è¦ªããèªåã®æ¯æ´ããã¦ã»ããã¨è¨ãããäºãæåã¯ç¶è¦ªãä¸ç·ã«é¿é£ããããæ¹è¨ãããããä½èª¿ãå£ã1å¹´ã§åç¸é¦¬å¸ã«å
ã«æ»ã£ããèªåãä¸çªèº«è¿ãªäººã®åã«ãªããªããã°ãªããªãã¨æã3å¹´ã§åç¸é¦¬å¸ã«æ»ã£ãã
ã»åç¸é¦¬å¸ã§ã¯è¿æã®äººãé¿é£ããã亡ããªã£ã¦ããããé¿é£åã¨åãã«ç¶æ
ã«æ»ã£ã¦ããªãäºã«æ°ãã¤ãããã¹ã¼ãã¼ã¯19æã«ã¯éåºããã³ã³ãããé¤æä½æ¥å¡ã®ç·æ§ãå¤ããã¬ã¸ã§ãããããã¦ããã¨å«ãããã³ã³ããã«ãè¡ããããªããªã£ãã
ã»å»çã®éçåãèãããç®èç§ã¯å
¨é¨ãªããªããå°é«åºã«ãã£ãç®èç§ãåçºã«ãªã¼ãã³ããããåã©ãã¨é«é½¢è
ã®æ£è
ãå¤ããæ°è¦ã®æ£è
ã¯ãã°ããåãä»ããªãã£ããããé£ã®ç¸é¦¬å¸ã¾ã§ä¸æ¥ãããã§éé¢ãä¸ä¾¿ãæãããé¤æä½æ¥å¡ã®å¥åº·è¨ºæã§ç·åç
é¢ã¯æ··ãã§ãã¦ãå½æã¯ã©ãã®ç
é¢ãæ£è
ã§ãã£ã±ãã ã£ãã
ã»æ£ããæ
å ±ãå¾ãäºãå¿æãèªåã®ä¸ã§ã©ã¤ã³ã決ããã
ã»åç¸é¦¬å¸æ°ã¯ã¬ã©ã¹ããããç¡æã§ãããããã¼ã«ããã£ã«ã¦ã³ã¿ã¼ãå¹´ã«1åç¡æã§åãããããèªå®
ã«ããç¶è¦ªã¨å¤åºã®å¤ãæ¯è¦ªãè·å ´ã«ããèªåã¨æ°å¤ã®æ¯è¼ãã§ãããéç½å¾ã®3å¹´éã¯é¤æãããã帰éå¾1å¹´å¾ã®é¤æã§ã¯å±æ ¹ãæå¾ã«ãªã£ãçºãæ°å¤ã¯é«ãã£ãã
ã»ç¸é¦¬å¸ãåç¸é¦¬å¸ã浪æ±çºã¯éç½ã®ç¶æ³ãé¿é£è
ã®æããã°ãã°ãã§ããã®3ã¤ã®ã¨ãªã¢ã§ä»äºã«éãä½æ°ã¨æ¥è§¦ãã¦ãæ¯æ´å¡æ代ã«æããäºãæã£ã¦ããäºã¨çãåãããã¦ããäºã§å
±æãèªåãæé·ã§ããã
ã»æ»ã£ã¦ããå°±ããæè²æ¯æ´ã®è·å ´ã¯ãå±±éã«ãã津波被害ããªãã£ãããçºéé害ã§æ´¥æ³¢è¢«å®³ã«éã£ãåã©ãã®æ¯æ´ãããããã®åã¯ã¿ããªã¨éãã¨ããæãããããå¦æ ¡ã«é¦´æããªãã£ããï¼ï¼ï¼ã®ã¤ãã³ãã®æããå¿ãããã®ã«å¿ããªãã§ï¼ã£ã¦ã©ããã¦è¨ãã®ï¼ãã¨èããããã®æ°æã¡ã¯ãããããããã§ããã®æ°æã¡ã誰ãåãããªãã®ã¯æãããªãï¼ãã®æ°æã¡ãã¿ããªã«ç¥ã£ã¦ãããã®ã¯å¤§äºãªäºã ãããã¨çãããããããã£ããã«å
æ°ã«ãªã£ããè¾ããã¨ãä¹ãè¶ããç¬éã ã£ãã®ãããããªãã
ã»è»¢å¤å¾ã®å°å¦æ ¡ã¯é²ç½ãéç½ã«åãå
¥ãã¦ããå°å¦æ ¡ã§ãããæ¯æ´ãããåä¾ã¯ãæ¬æ¥ã¯æ¯æ´å¦æ ¡ã«è¡ãã¬ãã«ã®åã ã£ãããä¿è·è
ã®å¸æã§é常ã®å°å¦æ ¡ã®æ¯æ´å¦ç´ã«å
¥ã£ããé¿é£è¨ç·´ã®æã«ãã津波ãæ¥ãã®ï¼ãã¨èãããè¨ç·´ãããã¨æ´¥æ³¢ããã¦ãæããªãããã¨ä¼ããããã®åã¯ä¸çæ¸å½è¨ç·´ãããã
ã»2å¹´éã§ç¸é¦¬å¸ã«åã©ãããã親ã®æ°æã¡ãããããã£ããã¡ãã£ã¨ããè¨èã®ããã¨ãã§å¯ãæ·»ãæ¯æ´ã¯å¤§äºãç¸é¦¬å¸ã¯é¿é£æ示ã¯åºã¦ããªãããåç¸é¦¬å¸ã浪æ±çºã®äººã¨æ°æã¡ã¯åãã§ãä¹ãè¶ãããã¨é å¼µã£ã¦ããã
ã»å®¶æã®äºæ
ã§ãåæ¥ã®äºåã®ä»äºããã£ã浪æ±çºã¸ã®ç¾å ´äºåæã«å¤åã決ã¾ã£ãã
ã»åæµ·éã®æ¥è
ãä¹å·ããããã¦ãããä½æ¥å¡ã«ä¸å®ã¯ãªããèãããããåã©ãã¯ãã§ã«å¤§ãããèªåã«ããã§ããªããããã¨è¨ããã¦ãããããã£ããè£æ¹ã§é å¼µã£ã¦ãã人éã«ä¼ãã¦å¿æ¸©ã¾ãæ°æã¡ã ã£ãã
ã»æµªæ±çºæ°ã§ã復èå£å°ã«ä½ãã§ããé«é½¢è
ã被ç½ããèªå®
ããã¿ã³ã¹ã¨ããã¤ãéã³åºãããã¨è¨ã£ãã社ä¼ç¦ç¥åè°ä¼ã«ç¸è«ãã¦ããã©ã³ãã£ã¢ã«æ¥ã¦ãããéã³åºãã¦ããã£ããã¿ã³ã¹ãã³ã¿ããéã³åºãã¦å®éã«å¿
è¦ã®ãªãç©ã ã¨èªåã§ç´å¾ããã°ããããã¦ãæ°ããå ´æã§çæ´»ãã§ãããªã大äºãªäºã ã
ã»å®¶ãåå°ãå¦åãã¦å°é«åºã§èªå®
ãè³¼å
¥ãã人ã¯ãè¿æã®ç°å¢ãéãåå°ã§ã®çæ´»ã§å¤§å¤ãªæããããã¨è©±ãèãããèªåã®æãæãã¦ãããã®ã¨éãçæãé·æãããã
ã»ç¡ç é害ã鬱ã«ãªã£ã¦è¬ãããã£ã¦ãã人ãå¤ããéç½ç´å¾ããã5ã6å¹´å¾ã«æ°ããªã¡ã³ã¿ã«ã¯ãªããã¯ãéæ¥ãã¦ããã
ã»æ»ããæ»ããªããã決ãã¦ãããé¸æè¢ããªããªã£ãäºã§æ©ãã§ãã人ããããæ»ããªãã¨é¸æããããã§é å¼µããªã人ã¯ä¸äººã§ã¯ç«ã¡ç´ããªãã®ã§ãã®å ´æã§ã®æ¥½ãã¿ãçããããããã°ããã決å®å¾ã大äºã§ããã
ã»æµªæ±çºæ°ã®ç¥ãåãã¯å¾©èä½å®
ã«ä½ãããã«ãªã£ã¦ããã太ã£ã¦å¬ããã¨è¨ã£ã¦ãããæ®æ®µããèªåã§ã¯ãã¡ãã¨é£ã¹ã¦ããã¤ããã ã£ãããæ°æã¡ãç·å¼µãã¦ãããã¨ã«æ°ãä»ãããä»ã¯ãã£ããé£ã¹ã¦ãå¤åºãã§ããããã«ãªã£ãããã ã
ã»ç·æ§ãç¥ãåãã«ä¼ã£ã¦ã¤ãªãããã§ãã¦ããã人ã¨ã¤ãªããäºã§å
æ°ã«ãªãå¼ãããã人ãå°ãªããªã£ã¦ããã
ã»ä»¥åã¨ã¯éãç°å¢ã®ä¸ã§ãå±
å¿å°ã®ããèªåã®ãã¼ã¹ãã§ãã¦ãããã©ãããã°æ¥½ã«çæ´»ã§ããã®ãããã£ã¦ãã¦ããã
ã»ç¾å¨ä½æ¥ãã¦ãã浪æ±çºã§ã¯ãæã¡ä¸»ãããããªã家ã¨åå°ããããããããä½æ°ãããªãã¦ã許å¯ãåãã¦ããªãå ´æã«ã¯ãéæ©ãå
¥ãã¦ã¯ãªããªãã許å¯ãã¨ããªãã¨åæã«éæ©ãç½®ããã¨ãã§ããªãã
ã»åç¸é¦¬å¸ã§ã¯ãã¶ã¼ãããããé²ç½ããã¥ã¢ã«ãåºãã¦ãããæ¾å°ç·å¥åº·å¯¾çãè¨è¼ããã¦ããã
ã»ãäºæ
ç±æ¥å»æ£ç©çå¦åæ¥åç¹å¥æè²è¦ç¨ããåãããé¤æä½æ¥å¡ãåãã¦ãã¦å
容ãéç½å¾ãæ´ã«è©³ç´°ã«ãªã£ããç¦å³¶çã§ã¯è¦å®ãããåããªãã¨æ¥åã«æºãããªãããç¾å ´ã§ã¯èªåãåè¬ããã°ãä»ã®äººã«æè²ããã¦åè¬è¨¼ææ¸ãä½ãäºãã§ãããå°éçãªç¥èã身ã«çãèªåã®ç¶æ³ãç解ããä¸ã§å®¶æã親ããå人ãªã©ã«ã話ããã¦ããã
ã»æµªæ±çºã®æä½ãã¢ã¼ãã£ã¹ãããã¤ã³ã¿ã¼ãããã§æä½ãã¢ã¯ã»ãµãªã¼ã販売ãã¦ãããããã°ããµã¤ããè¦ãã¨å
æ°ã«ãªãå¨ããæãããªã£ãã
ã»æµªæ±çºã«å²ãã¦ããè±ã
ã¯å
æ°ã«å²ãã¦ãã¦å±ã¾ãããã
ã»åçºåºã«æµªæ±çºã®å¾©èå£å°ããããéç½åã«æµªæ±çºã«ãã£ãã¹ã¼ãã¼ãã¼ã±ããããããããã«è¡ãã°å人ã«ä¼ããçºãæ°æã¡ãååãã«ãªãã
ã»æ¾å°ç·æ¸¬å®ã»ã³ã¿ã¼ã§æ¾å°ç·ã®ç·éããããããããææ°æ
å ±ãç¥ããã¨ãã§ããã
ã»åã©ãã®ã津波ãã£ããããå°éãã£ããã¯ã¨ã¦ãããã¨æããä¸å®ãæ±ãã¦ãããæ¯ããã¯å¤ãã親ãä¸ç·ã«ããã£ãéã³ããããªããéã³æè¦ã§è¨ç·´ã§ããã¨æãã
ã»æéã®çµéã¨å
±ã«å¤ãã¦ã¯ãããªãé¨åã¨å¤ããæ¹ãããé¨åãå¼ãç¶ãèããªããè¡åãã¦ããã
ã»é¤æãçµãã£ãã®ã§ãçºã®é°å²æ°ã¯å¤ãã£ãã浪æ±çºã解é¤ã«ãªãä½æ°ã®åºå
¥ããé »ç¹ã§ã³ã³ããã®å¥³æ§å®¢ãå¢ãããã¾ã ä¸é¨é¤æä½æ¥ã¯ç¶ãã¦ãããå
¨ä½ã§ã¯çµãã£ã¦ããã®ã§ãå¤ã®ã³ã³ãããè¡ããããã«ãªã£ãã代è¡è»ãã¿ã¯ã·ã¼ãæ¥ãããã«ãªã£ãã
ã»å°é«åºã解é¤å¾ã¯é«é½¢è
ãä½æ¥å¡ãå¤ãã£ããä»å¹´ã®æ¥ããé«æ ¡çã«ããã«ãè¦ãããããã«ãªã£ãã
ã»å°é«åºã¯ãã¡ããªã¼ãã¼ããã§ããã浪æ±çºã«ã¯æ¥å¹´å¾©èä½å®
ãå®æããã³ã³ãããããã«1件å¢ãå¶æ¥æéãé·ããªãã
ã»åç¸é¦¬å¸ã¯é²æ³¢å ¤ãã§ããæ²»å®ã¯å¤§ä¸å¤«ã ãéæ£ã¨ãã¦ããã人æ°ãå°ãªãã®ã§éå£ç»æ ¡ãã§ããªãå¦æ ¡ã¯ããããæ©ãã¦ç»æ ¡ãã¦ããã人ã¯å¢ããã