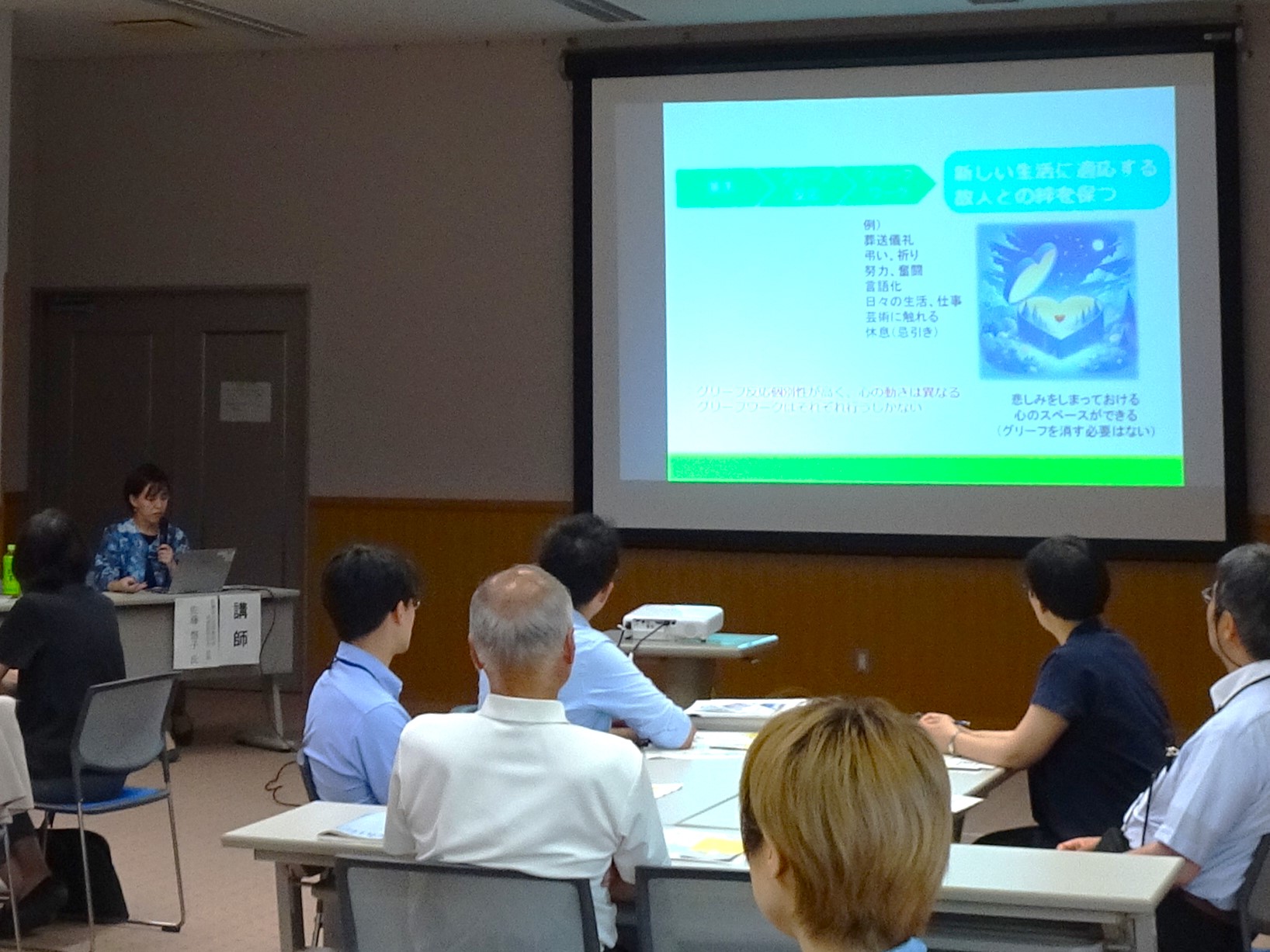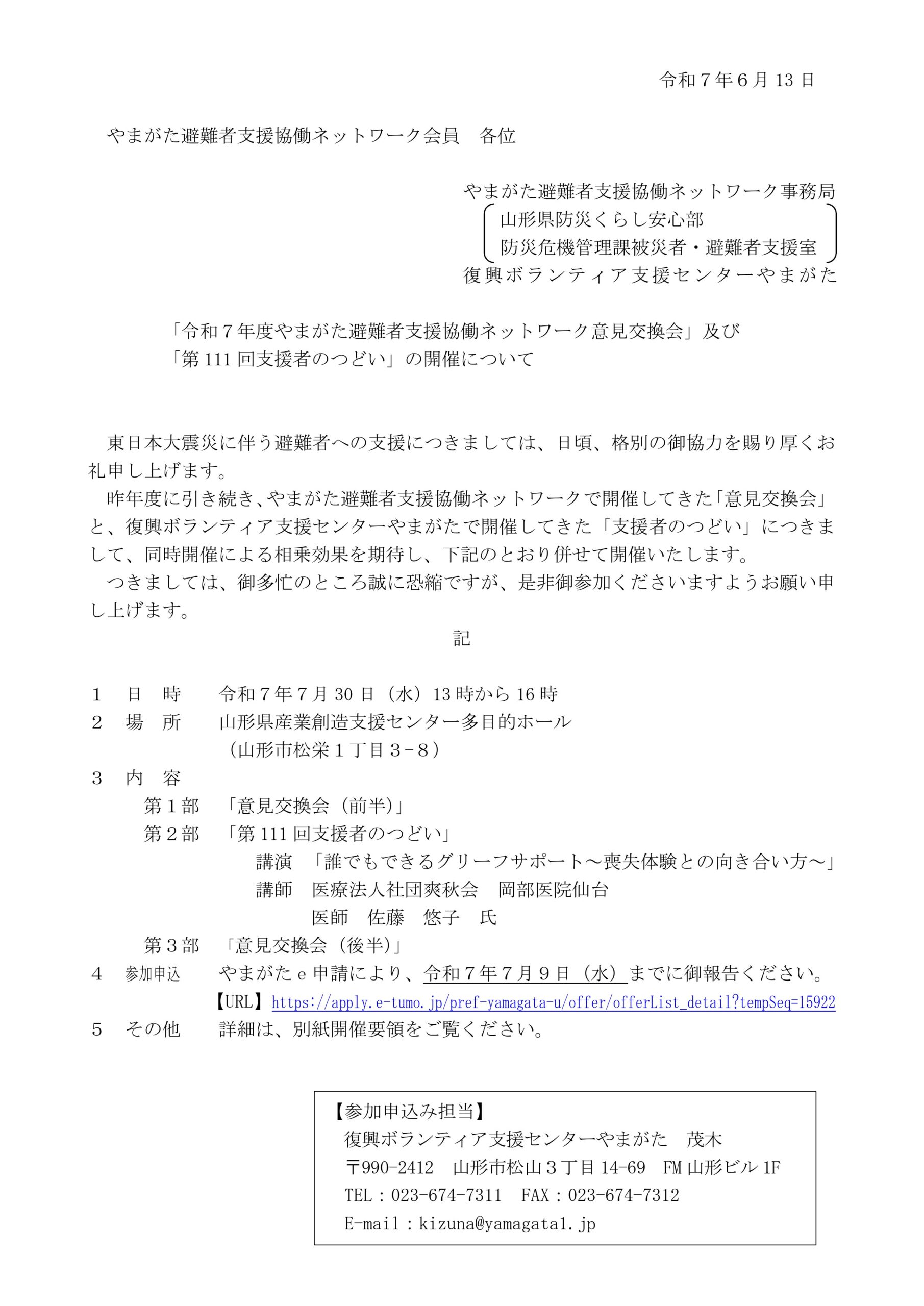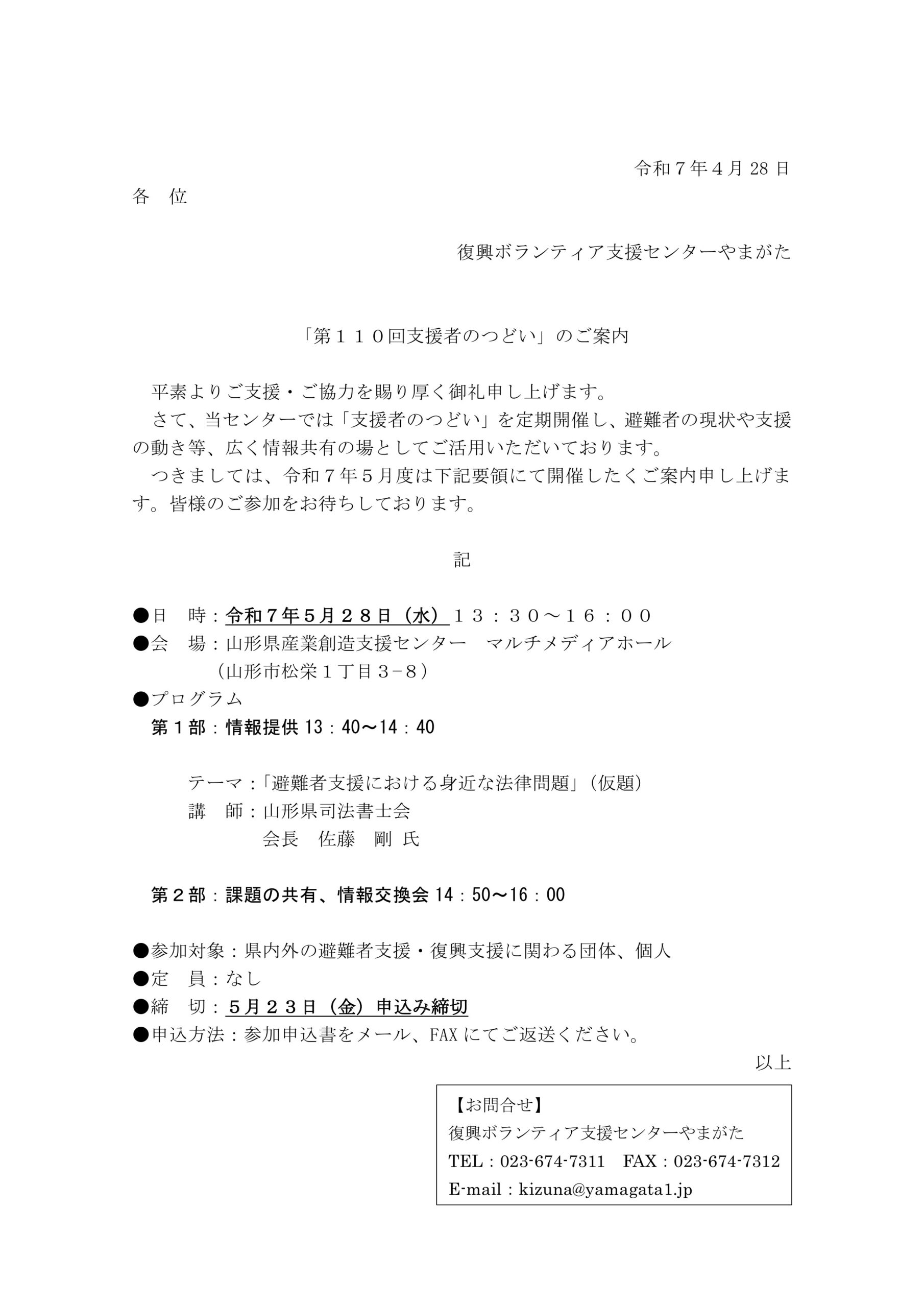â 第2é¨ãæ´»åå ±åãç¾ç¶ã課é¡ã®å ±æâ
<æ´»åå ±å>
ã»çå
ã®åå
¥ç¶æ³ã¯ã9æ7æ¥ç¾å¨ã§2,021åã721ä¸å¸¯ã8æ2æ¥ã§ã¯ã2,026人724ä¸å¸¯ã§5å3ä¸å¸¯æ¸å°ãã¦ãããæ°éåä¸ä½å®
ã¯ã40ä¸å¸¯ã®82åã§å
æãã1ä¸å¸¯2åã®æ¸ã§ããã
ã»7æ20æ¥ã¾ã§ãé¿é£è
ä¸å¸¯ã¸8åç®ã®ã¢ã³ã±ã¼ã調æ»ãããã702ä¸å¸¯ã«éä»ã200件ã®åçãããã£ããååçã28.5ï¼
ã§ãæ¨å¹´åº¦ããä¸ãã£ããçµæã¯9æ13æ¥HPã§å
¬éããä»å¾ã®é¿é£è
ã®æ½çã«åæ ãããã
ã»7æã«ãçæ´»æ¯æ´ç¸è«å¡7åã¨ç社å2åã§ãåç¸é¦¬å¸ã®ç¤¾åã¨æµªæ±çºã«è¦å¯ã«è¡ã£ããä»å¾ã®è¨ªåæ´»åã§å½¹ã«ç«ã¤æ
å ±ãå¾ããã¨ãã§ãããæ¥å¹´ãåç¸é¦¬å¸ã§1å¹´å¾ã®å¾©èã®åå¼·ããããã
ã»8æã®2åç®ã®èª¿æ´ä¼è°ã§ã¯ãæ°çå§å¡ã«ã¤ãã¦å¦ãã ãä»å¾ãé£æºãã¦ããããæ¯æ´ããããã
ã»æµªæ±çºã®å°ä¸å¦æ ¡ãéæ ¡ããå°å¦çã¯8åãä¸å¦çã¯2åãåè¨10åãéã£ã¦ãããé£ã¯èªå®ãã©ãåã§13åãéã£ã¦ããã
ã»ç±³æ²¢å¸ã§ã¯ãããããä¿è²ããã®å主å¬ã®ããããã¨ããã«ã·ã§ããéå¬ãããã©ã¤ããbinoåºåºã®ã³ã¼ãã¼ãæä¾ããã
ã»é¸åé«ç°å¸ã¨å¤§æ§çºãä¼æ´¥è¥æ¾å¸ã§ãæåæ謡ã¨å¯¾è©±ã«ãã§ãéå¬ãããç¹å®ã®å
¬å¶ä½å®
1ãæã§éãã®ã§ã¯ãªããä»ã®å°åã§ãå°åä½æ°ã交ããããããå«è¶ãéãã
ã»ãã©ãå¿ã®é²ç½å£«ã§çµµæ¬ã®æ´»åããã¦ãããçµµæ¬ãéãã¦åçºæ´»åãããæ ç»ãä½ãããã
ã»æ¥å¸°ãæ
è¡ã«è¡ããåå è
ã¯11åã ã£ããã大å¤åãã§ããã
ã»ç¬¬2ã¨ç¬¬4ææ10æãã13æã¾ã§ããè¶ã¡ãã®ä¼ãã第3æ°´ææ¥ã¯ãè±ã¯ãªä¼ããéå¬ãã¦ãããå
æ¥ã¯8åã»ã©ã®åå ã§ãã£ãã
ã»æ±æ¥æ¬å¤§éç½ã®æãã¬ã½ãªã³ã»é£æã»è¬ãè²·ããªãã£ãäºãªã©ããçæ¿ãå¼µãç´ãå½æã®ç¶æ³ãæ®å½±ãã¦ãããã¥ã¡ã³ã¿ãªã¼æ ç»ã§ã¾ã¨ãããæ±äº¬ãç³å£å³¶ã§ãä¸æ ãããç¦å³¶ã»å®®åã®å¾©èãå¿ãã¦ã¯ãããªãäºããã¾ãã¾ãªå ´æã§ä¼ããã
ã»å±±å½¢å¸å
ã®æ¹ã«æ¯æãç¥ãããéã£ã¦ããããã©ã·ãªã©ä¸ç·ã«çºéãã¦ã»ããæ¹ã¯ç¸è«ãã¦ã»ããã
ã»å
æ¥é£¯é¤¨æã«è¡ã£ãã飯館æã®åºèã¯ç«æ´¾ã§ãã£ããéåæ½è¨ã»ç
é¢ã»ä½å®
ããã£ãããåãå£ãã®å®¶ããããèåãã¯ããã¦ããããä½ç©ã¯æ¤ãã¦ããªãã£ããéã®é§
ã¯ãªãªã³ããã¯ã«åãã¦è±ãæ ½å¹ãã¦ããã
<ç¾ç¶èª²é¡>
ã»æ¥å¹´ã®3æã§åãä¸ãä½å®
ãçµäºãããããå¿é
ãªæ¹ãä½äººãããã家æéã§ã®ç¸è«ãã§ãããå¼è¶ãããããã©ãã«ç¸è«ãããããã®ãããããªãããããªãã¦ã¯ãªããªãäºãèªåã§ã§ããªãã®ã§ãç¸è«å¡ãä¸åç£å±ã«è¡ãæç¶ããªã©ç¸è«ãã¦ããã
ã»ç¸è«å¡ã¯ãäºæ
ã«åãã¦è»ã«é¿é£è
ãåä¹ãããäºãã§ããªããå¾
ã¡åããããããç©ä»¶ãã³ãã¼ãã¦å±ããããã§ããªãã
ã»åæµ·éã§ã®å°éç½å®³ããæ¸æ²¢æã®æ°´å®³ãªã©èº«è¿ã«èµ·ãã£ã¦ãã¦ãé²ç½ã¯é¢¨åããã¦ã¯ãªããªãã
ã»åæµ·éå°éã®æã¯ãåæµ·éã§ä¼è°ãããé£çµ¡ãã¤ããªãã¦å¤§å¤ã§ãã£ããæå¹å¸å
ã®é¿é£æã¨ãæ¸
ç°åºã®æ¶²ç¶åç¾è±¡ã¨å
¨å£ã»åå£ã®å®¶ãããæã«ãè¡ã£ããé¿é£æã«ã¯ã39åã®æ¹ãé¿é£ãã¦ãããã山形ã®é¿é£æã¨ã¯éã£ã¦ãæ¯æ´ç©è³ãå¿ã®ã±ã¢ãããã¦ããªãã£ãã
ã»é«éãã¹ã§ãããå¸ã«è¡ã£ããåçºã«è¿ãå ´æã§ã¯æ¾å°ç·éã®æ°å¤ãé«ããªããé«ééè·¯ã家ãæ´åãã§ãã¦ããªãã®ã§ãæ±æ¥æ¬å¤§éç½ã®æã§ç¶æ³ãæ¢ã¾ã£ã¦ããã
ã»é¿é£è
ã®äººãææ¥è»ã§æ¬éããããè¿ãã«è¦ªæãããªãã¨ä»ãæ·»ãã®å®¶æã帰ãæ段ããªãã
ã»å¦æ ¡ãæææ¥ä¼ã¿ã®æ¥ã«åã©ããé ãã£ããç§å¦åç©é¤¨ã«è¡ããã¨ããããæææ¥ã¯ã©ããä¼ã¿ã§å®®åçã§ãéãã¦ããã¨ããããªãã£ãã
ã»å²¡å±±çã§ã¯å人æ
å ±ãå
±æãã¦ããã山形çã§ãã¾ã¨ã¾ãã°ããã¨æãã
<åç¥>
ã»æè¦äº¤æä¼ã10æ1æ¥ã«çåºè¬å ã§éå¬ããããã¼ãã¯ãä»å¾å¿
è¦ãªé¿é£è
æ¯æ´ãèããï½é¿é£è
ã®ã¤ãªããã¥ããï½ãã§æ´ç°é¦æå
çã«è¬å¸«ã§æ¥ã¦ãããã
ã»11æããå
¨æ¸è¨ªåãå®æ½ããããã説æä¼ã¨æ
å ±äº¤æä¼ã10æ15æ¥åºå
ã18æ¥æå±±ã»æä¸ã»ç½®è³å°åã§éå¬ããã
ã»11æ16æ¥ï¼éï¼ã«3åç®ã®èª¿æ´ä¼è°ãéå¬ãä»åã¯ãåæ¥ãå¸çºæ社åã®å°åç¦ç¥æ
å½è·å¡ã対象ã«ãã¦ãæ¯ãåãå°åç ä¿®ä¼ãäºå®ãã¦ããã
ã»ç±³æ²¢å¸ã§ã¯ã10æã«æè·å¡çµåãèç
®ä¼ãäºå®ãã¦ããã
ã»ãã¡ã¼ã©å¸æ°ä¼ç»è¬åº§ã§ã10æ7æ¥ã«ããã¥ã¡ã³ã¿ãªã¼æ ç»ãä¸æ ããããç£ç£ã岡å´åããã§ä»¥åããç§ãã¡ã«ã§ããäºã§ããªãã£ãäºããä¸æ ããçµç·¯ããããä»åã®æ ç»ãã¢ã¼ã«ã¤ãã«ä¿åããã¦ãã¦ãæ¸è°·ã®é²ç½ãã§ã¹ã¿ã§ä¸æ ä¼ããããéªç¥æ·¡è·¯å¤§éç½ã»æ°æ½ä¸è¶å°éã»æ±æ¥æ¬å¤§éç½ãä½é¨ãã女æ§ãç»å ´ããã
ã»11æ18æ¥ã«ãç¦å³¶çã®ç¸è«ä¼ãã山形å¸é¿é£è
交æµæ¯æ´ã»ã³ã¿ã¼ãã§éå¬ããã
ã»10æã«éèæãã¨èç
®ä¼ãäºå®ãã¦ããã
ã»æ¯æ´è
ã¹ãã«ã¢ããç ä¿®ä¼ãéå¬ãããå¾è´ã®è¬åº§ãã10æ25æ¥ã»26æ¥ã«ãä»å°å¾è´ã®ä¼ã代表çäºæ£®å±±ããã«è¬å¸«ã«ãã¦ãããéå¬ããã
<質çå¿ç>
Qæ°é±éåã«ãç¦å³¶çé§å¨å¡ã訪åã«æ¥ãã¨é¿é£è
ãè¨ã£ã¦ããããã¾ãå
¨æ¸è¨ªåããã®ãã
Aç¦å³¶çããã®é§å¨å¡ã¨å¾©èæ¯æ´å¡ã§ãç¸è«å¡ã®ããªãå°åã訪åãã¦ãããä»åã¯æ¯å¹´1åãçã®äºæ¥ã§è¨ªåããã¦ããç¸è«å¡ã復èæ¯æ´å¡ã®è¨ªåã¨ã¯å¥ã«è¡ã£ã¦ãããä»å¹´ã¯ãç±³ãæã£ã¦è¡ãã
Qå
¨æ¸è¨ªåã§ãçæ´»ç¶æ³ãå°ã£ã¦ããäºãªã©ã®å
±éã®è³ªåã¯ããã®ãã
Aæ¨å¹´ã¨åãå
容ã§å
±éã®è³ªåäºé
ã¯ããã
Q訪åæ¥ã¯åæ¥ããåãã¦ãã人ãå¤ãã®ã§å¹³æ¥ã¯ä¼ããªãã¨æãã
Aé¿é£è
ã®ä¸é½åã«ãªããªãããã«ç¶æ³ã«å¿ãã¦è¨ªåã«ããã