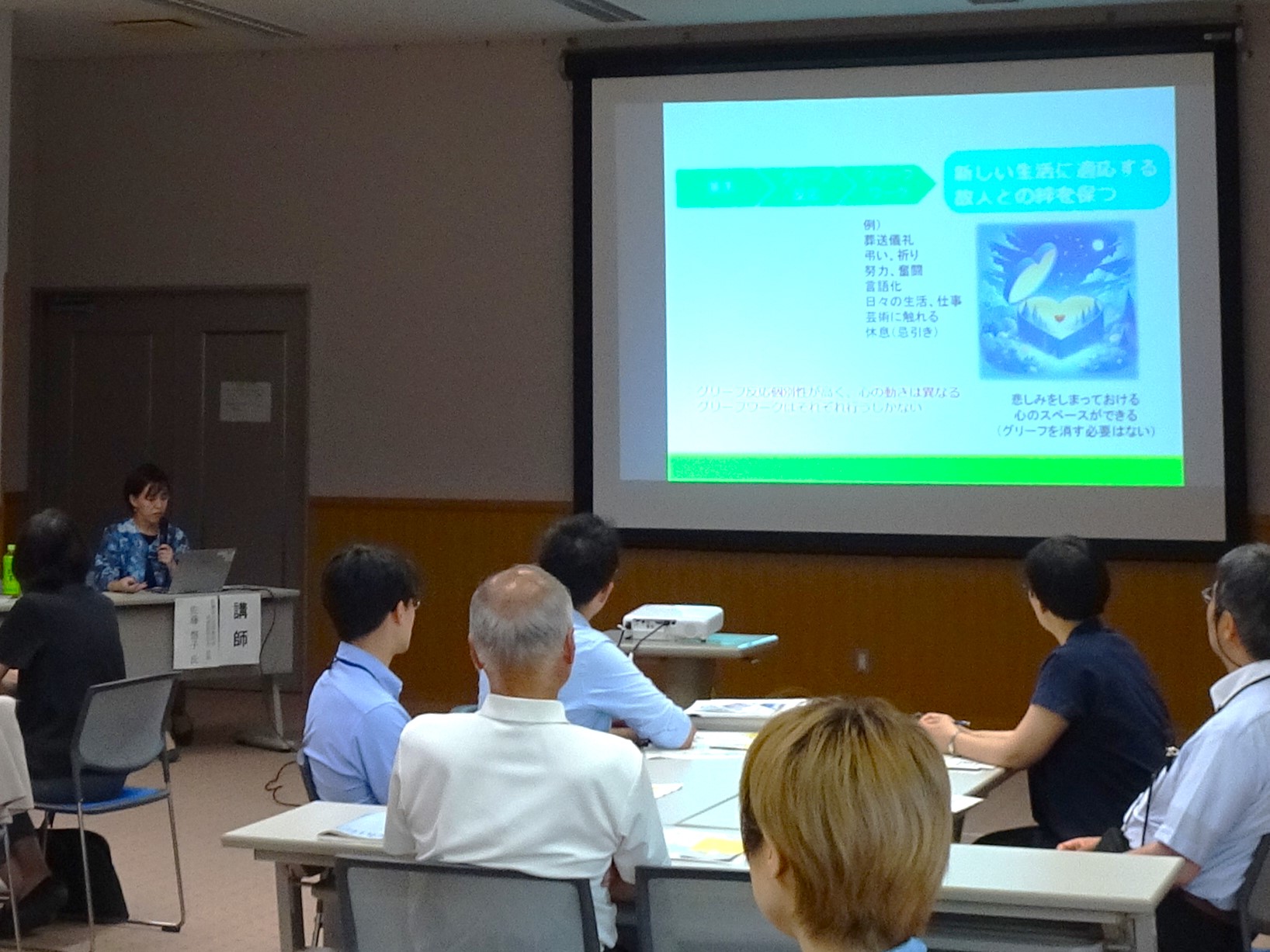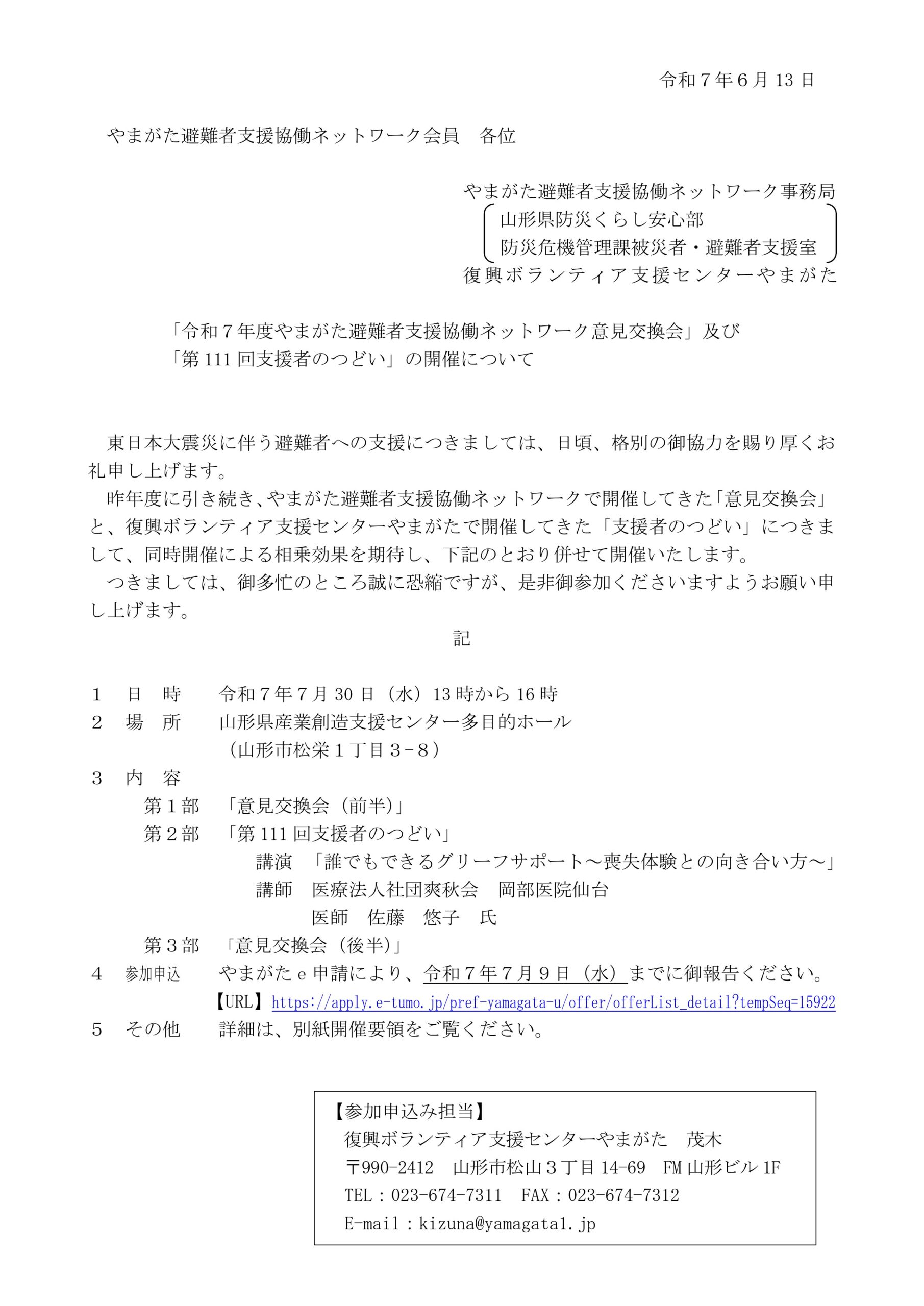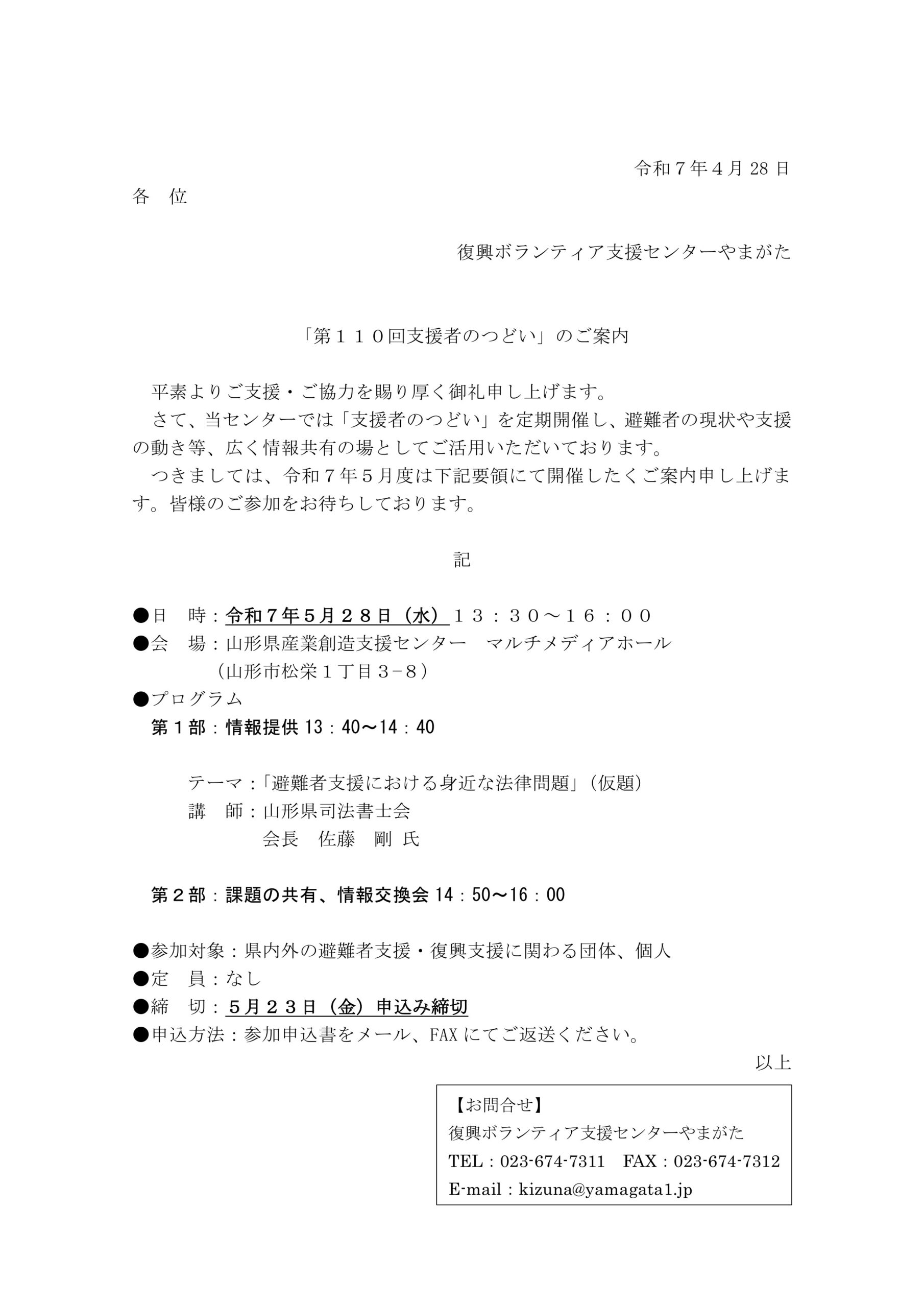平成31年4月25日(水)、山形市男女共同参画センター5F 視聴覚室を会場に、第83回「支援者のつどい」を開催しました。話題となった概要を広く皆様にお伝えします。ご参加頂きました皆様、ありがとうございました。
<参加者>
子育て支援団体 2団体
中間支援団体 2団体
カウンセリング団体 1団体
保養支援団体 1団体
山形県社会福祉協議会
山形県 復興・避難者支援室
山形市社会福祉協議会
朝日新聞社
参加者数:12名(9団体) 報道:1名 スタッフ:2名 計15名
■第1部 情報提供■
「保養支援についての情報提供」
提供者:311受入全国協議会 共同代表/Team毎週末みんなで山形
代表 佐藤 洋 氏
・避難をする、保養に行く事は同じ部分がある。
・他県に避難をすることができなかった子どもや親子が、一定期間、他県で心身ともにリラックスできるのが保養である。
・「Team毎週末みんなで山形」は、みんなで活動している意味も含めて名前を変えた。
・被災者支援をするきっかけは、福島の知人が自宅に避難してきたために、状況を詳しく知ることができた。今、自分が支援をしないと後悔すると思った
・チェルノブイリの事故の後に保養と呼ぶようになった。保養は、身体の回復を目的としたもので、まとまった期間療養をする。放射線被曝の回復が根底にはあるが、里山で自然を取り戻す目的もある。震災直後は自然の中で遊ぶ事を奪われたので、自然がいっぱいの山形県は場所がたくさんあった。
山形なら安いコストで保養ができる。
・保養では不安を自由に話せる。メンタルのケアは重要である。
・保養の社会的位置づけの変化は、震災初期(2011年から2013年頃)様々な被災者支援活動の内の一つとして、社会的に受け入れられ報道でも好意的に取り上げられていた。
2014年から2016年頃は、参加者は友人に保養参加を殆ど表明できない状態になった。保養の情報が拡散されず、比較的小さな輪の中で認識されるようになり、保養と言わずにリフレッシュキャンプと呼ぶなど配慮しながら継続した。最初は、年間8,000人ほどの利用者がいたが、現在は参加しにくくなっている。避難と同じで今後考えていかなくてはならない。
・保養で健康講座をした。参加者に健康に気を使っている事を聞いたら、昨年から子どもを外で遊ばせていると話した。震災直後には聞けなかったことで時間の経過を感じた。
・保養の最大のテーマは不安表明をする権利を守る事。「それぞれに悩む」というお互いの状態を「受け入れる」と言う約束が出来る状態が理想。
・1998年1月にウイングスブレットで科学者や弁護士が集まり話合い宣言を発表した。
【ウイングスブレット宣言…… 毒性物質の放出、資源の採掘、環境の物理的改変によって、重大かつ意図しない影響が環境と人間の健康に発生している。たとえば、学習障害や喘息、がん、先天性異常、種の絶滅が高い率で発生したり、地球規模の気候変動や成層圏のオゾン層破壊が進行したり、世界各地で有害物質や放射 性物質による汚染が広がったりしている。 既存の環境規制やその他のさまざまな決定、特にリスクアセスメントを基礎としたものによって、人間の健康および人間がその一部にすぎないより大きなシステムである環境を守ることはできてこなかったと我々は考える。人間および地球環境に対する被害は、あまりに大規模、かつ深刻であり、人間活動の指針となる 新たな原理が必要なことを示す、確固とした証拠があると我々は考える。人間の活動によって危険が発生することがありうるのは確かだが、物事の進め方を近代において 行ってきたよりも慎重に物事をすすめなければならないのだ。企業や政府機関、組織、地域社会、 科学者、その他の人々のすべてが、あらゆる人間活動に対して予防的アプローチを採用する必要が ある。よって、そのために予防原則を実現しなければならない。ある行為が人間の健康や環境に対する脅威であるときには、その因果関係が科学的に完全に解明されていなくとも、予防的方策をとらなければならない。予防原則では、立証責任は、市民ではなく、その行為を推進しようとする者が負うべきである。予防原則の実現プロセスは公開された民主的なものでなければならず、また、影響を受ける可能性のある関係者のすべてが参加していなければならない。活動自体の取りやめを含む、あらゆる代 替策の検討も必要である。】
保養団体はこの宣言を心の支えにしている。
・震災後、原子力被災地の人々が奪われている最大の物は、放射能災害の影響について「心配であるということを表明する権利」であり、最悪の事態に備える、という予防原則に基づいたアクションを禁じられている事である。地震・津波は事前に備える事ができるが、原子力のついては禁じられている。
・311受入全国協議会は2012年発足で、年に数回保養相談会を開催している。現在は60団体前後が加入している。
・保養は空き家、キャンプもある。葉っぱ塾は朝日自然観で、鶴岡市で空き家を提供している団体もある。山形市内ではお寺での週末ステイがあったが今は休止中である。
・山形県を県外の団体が保養として使っている。
【質疑応答】
Qほよ~ん相談会では、終了後の反省会でどんな話題がでるのか。
A相談会は全国の団体が集まる。どんな人が参加していたのか、どのような傾向なのかなどの話題がでる。
Q運営側では、金銭以外で課題になっている部分は何か。
A寄附金で活動をしているが、震災直後と現在を比較すると大変になってきている。関西では交通費を負担している団体があったが、参加者のモラルの問題で悩みもあった。少額で活動をしているので、今後ルールをきちんと決めて活動するしかない。
Q「被災者自身の力を信じる」とはどんな行動をしているのか。
Aお客さまとして迎えずに、食事も掃除も一緒に家族として過ごす。
Q参加している人は、リピーターと初めての方の割合はどうか。
Aここ数年では95%がリピーターで初めての人は5%で、初めての方も他の保養には参加していたため、保養のリピーター率は高い。