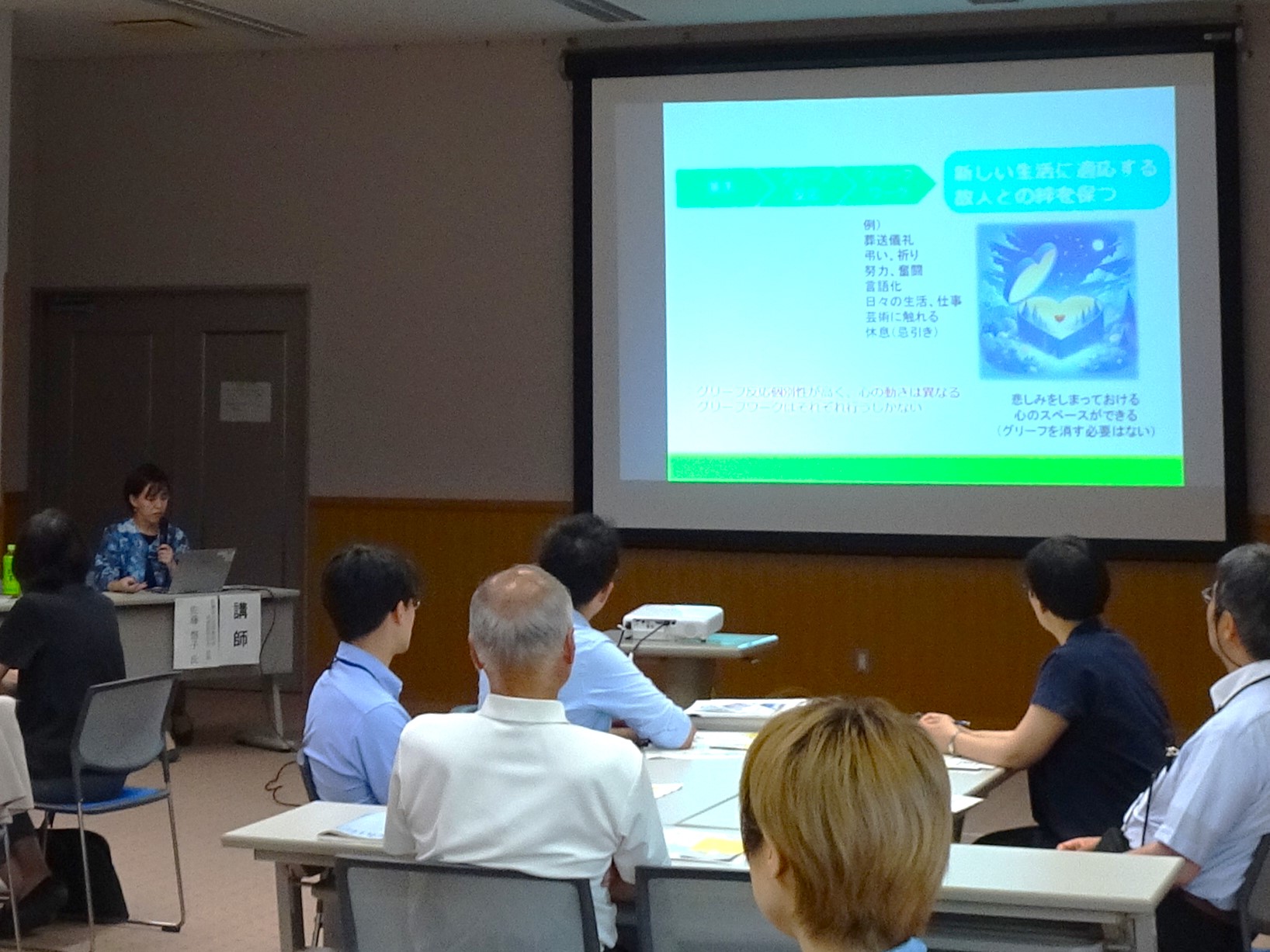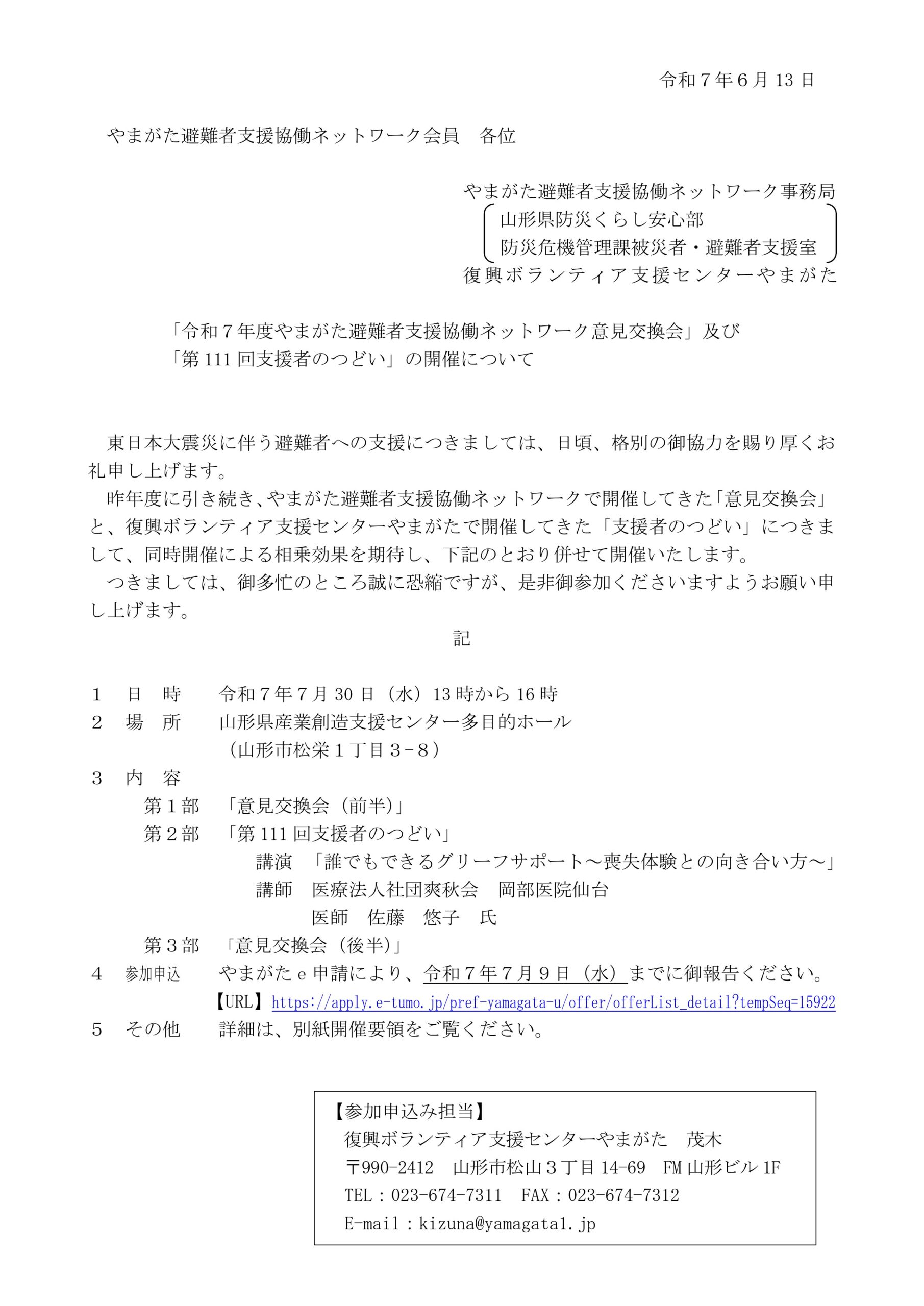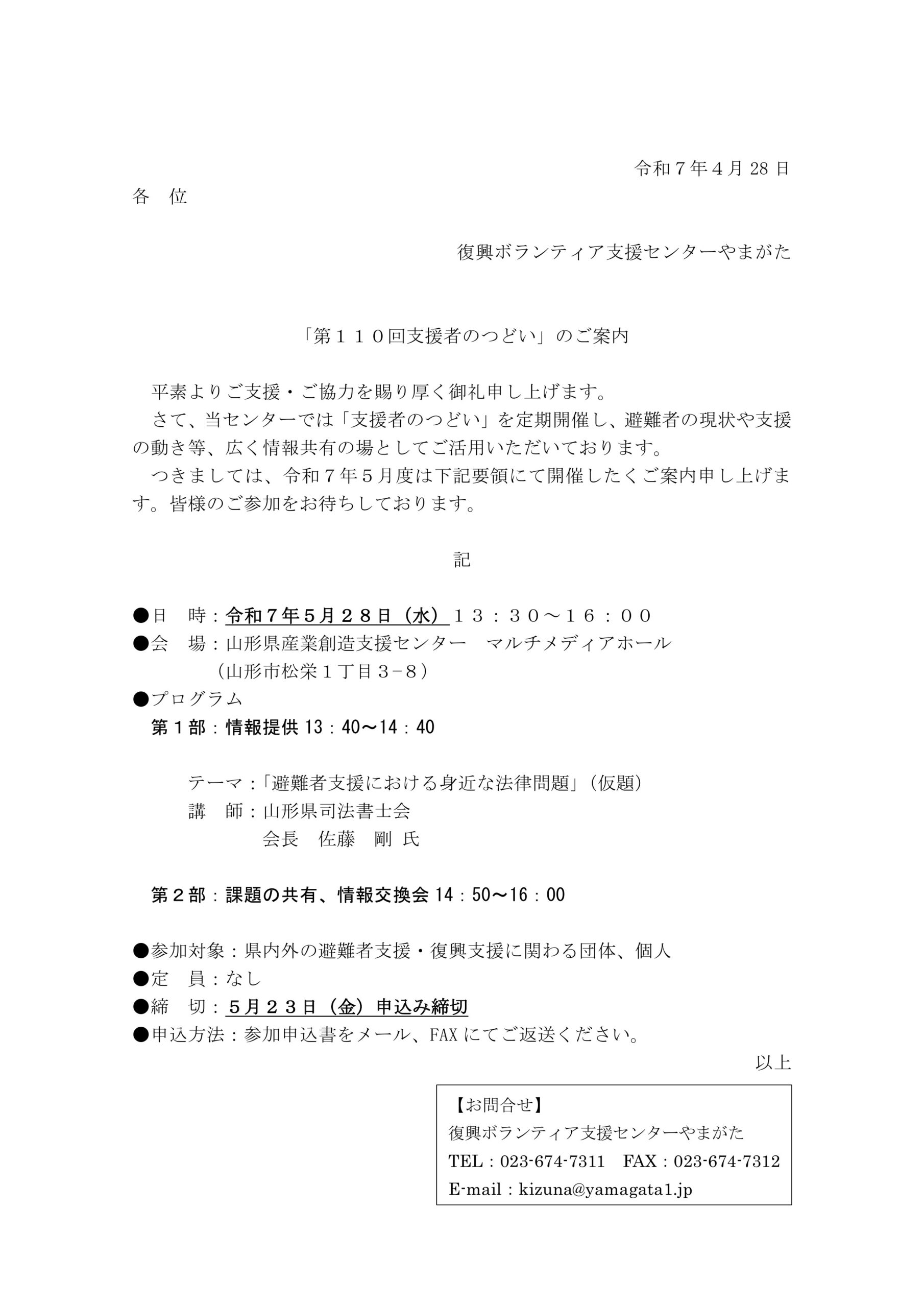第ï¼ï¼åãæ¯æ´è ã®ã¤ã©ãã話é¡æ¦è¦ã
å¹³æ28å¹´11æ30æ¥ï¼æ°´ï¼ã山形å¸ç·å¥³å
±ååç»ã»ã³ã¿ã¼ãä¼å ´ã«ã第61å ãæ¯æ´è
ã®ã¤ã©ãããéå¬ãã¾ããã話é¡ã¨ãªã£ãæ¦è¦ãåºãçæ§ã«ãä¼ããã¾ãã
ãåå é ãã¾ããçæ§ããããã¨ããããã¾ããã
ï¼åå è
ï¼ï¼â»ç³è¾¼é ãæ¬ç§°ç¥ï¼
ã³ãã¥ããã£æ¯æ´ã1å£ä½
æ
å ±æ¯æ´ã1å£ä½
ã«ã¦ã³ã»ãªã³ã°ã1å£ä½
ä¸éæ¯æ´ã1å£ä½
é²ç½å£ä½ã1å£ä½
天童å¸ç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼ã
山形å¸ç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼
米沢å¸ç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼
åé½å¸ç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼
é«ç çºç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼ã
山形ç社ä¼ç¦ç¥åè°ä¼
山形å¸é²ç½å¯¾ç課
山形å¸é¿é£è
交æµæ¯æ´ã»ã³ã¿ã¼
山形ç復èã»é¿é£è
æ¯æ´å®¤
ç¦å³¶çé¿é£è
æ¯æ´èª²
ãã®ä»ï¼å ±éã1社
åå è æ°ï¼25åï¼ï¼ï¼å£ä½ï¼å ±é1åï¼1社ï¼ãã¹ã¿ããï¼ï¼åããè¨30å
â 第1é¨æ¯æ´æ´»åã«é¢ããæ
å ±æä¾ããç¦å³¶ççæ´»æ ç¹èª²
ãæ°è³è£å©éã®ç³è«æç¶ãï½æ¯æ´è
ã®ããã®åå¼·ä¼ãã
âç¦å³¶çæ°éè³è²¸ä½å®
ç家è³è£å©äºæ¥è£å©éã®ç³è«æç¶ãã«ã¤ãã¦
ã»å±±å½¢çã«ã¯2700åã®é¿é£è
ããã¦ãèªä¸»é¿é£800ä¸å¸¯ã3æã§åãä¸ãä½å®
ãçµäºã¨ãªããè£å©éã®æ¦è¦ã®èª¬æã¨è³ªåãåãèªèãå
±æãããã
ã»æ¯æ´çã¯9æ27æ¥ã«å
¬è¡¨ãé¿é£è
ã«ã¯ãã¤ã¬ã¯ãã¡ã¼ã«ãéµéãªã©ã§ä¼ãã¦ããã
ã»å¯¾è±¡ä¸å¸¯ã¯ãé¿é£æ示åºåå¤ããå¿æ¥ä»®è¨ä½å®
çã«é¿é£ãã¦ããä¸å¸¯ã®ãã¡ãå¿æ¥ä»®è¨ä½å®
çã®ä¾ä¸çµäºå¾ãæ°éè³è²¸ä½å®
çã§é¿é£çæ´»ãç¶ç¶ãããã¨ãå¿
è¦ãªä¸å¸¯ã
ã»å±±å½¢çå
ã§è»¢å±
ãç¦å³¶çå
ã§ãé¿é£å
以å¤ã®å¸çºæã§ããã°å¯¾è±¡ã«ãªãã
ã»åå
¥è¦ä»¶ã¯æé¡æå¾ã214,000å以ä¸ã®ä¸å¸¯ã
ã»å¹³æ27å¹´12æ25æ¥ã®æ®µéã§ã¯158,000å以ä¸ã«ãã¦ãããããã®åºæºã§ã¯é©ç¨ä¸å¸¯ãå°ãªããªãã®ã§åºãã¦ã»ããã¨ã®è¦æããã£ãããè¦ç´ããããã
ã»æ¯åé¿é£ã®äºéçæ´»ã®å ´åã¯ãå¹´éæå¾ã2åã®1ã«ãªãã
ã»å®¶è³è£å©ã¯å¹³æ29å¹´ã®1æãã30å¹´ã®3æã¾ã§ã¯å®¶è³ã®2åã®1ï¼æ大3ä¸åï¼ãå¹³æ30å¹´4æããå¹³æ31å¹´3æã¾ã§ã¯å®¶è³ã®3åã®1ï¼æ大2ä¸åï¼ãè«æ±ãããã£ã¦ããã®äº¤ä»ã
ã»åæè²»ç¨ã®10ä¸åã¯äº¤ä»æ±ºå®ã«ãªã次第æ¯æãããã
ã»æ·»ä»æ¸é¡ã¯æå¾ã«å±
ä½ãã¦ããå¿æ¥ä»®è¨ä½å®
çã®å¥ç´æ¸ã®åããä¸å¸¯å
¨å¡åã®ä½æ°ç¥¨è¬æ¬ãä¸å¸¯å
¨å¡åã®å¹³æ28年度ã®æå¾è¨¼ææ¸ã
ã»è»¢å±
ã®çç±ã®è¨å
¥æ¼ãã®éã¯ã»ã³ã¿ã¼ããå度é£çµ¡ãããã
ã»å¼è¶ãè£å©ã¯å¸°éæ¯æ´ãæ°éä½å®
ã®å®¶è³è£å©ã¯é¿é£ç¶ç¶ã®æ¯æ´ãªã®ã§éè¤ã®ç³è«ã¯ã§ããªãã
ã»åå
¥ã«å¿ãã家è³è¨å®ããã¦ããªãå
¬å¶ä½å®
ã¯å¯¾è±¡ã«ãªãã
ã»è£å©éã®æ¯è¾¼å£åº§ã¯ãé¿é£ç¶ç¶ã®æ¯æ´ãªã®ã§ãå¿æ¥ä»®è¨ä½å®
ã«ä½ãã§ãã人ãç³è«ããéè¡å£åº§ãå±
ä½è
ã®å義ã«ãªãã
ã»æ¯åé¿é£åã¯ç¶åé¿é£ã®ãä½æ°ç¥¨ã§ã®äºéç活確èªã¯å³ããã®ã§ãå
Œ
±æéã®æç´°ãé«ééè·¯ã®æç´°ã証ææ¸ã«ãªãã
ã»9æ29æ¥ããç¦å³¶çæ°è³çè£å©éäºåã»ã³ã¿ã¼ãéæãç³è«æç¶ãç¸è«ã»åãåããã»å¯©æ»äºåã»è£å©é交ä»æç¶ããä¸æ¬ã§è¡ã£ã¦ãããé話æç¡æã§å¹³æ¥9æï½17æã«3åç·ã§å¯¾å¿ãã¦ããã
ã»æ°éè³è²¸ä½å®
ã®å¥ç´æ¥ãã3ã¶æå¾ã®å±ããæã®æ«æ¥ã¾ã§ï¼æé·ã§å¹³æ29å¹´6æ30æ¥ã¾ã§ï¼çãåçããå ´åãå¹³æ29å¹´1æåã®å®¶è³çããè£å©å¯¾è±¡éé¡ãç®å®ã§ãããã®ã¨ãã¾ãã
âå¼è¶ãè£å©ã«ã¤ãã¦
ã»å¯¾è±¡ã¯ãå¹³æ29å¹´3æ31æ¥ã¾ã§é¿é£å
ã®èªå®
ã«ã移転ã®å®äºä¸å¸¯ãè£å©é¡ã¯è¤æ°ä¸å¸¯100,000åãå身ä¸å¸¯50,000åãæåºæéã¯ç§»è»¢å®äºæ¥ããã3ã¶æãçµéããæ¥ã®å±ããæã®15æ¥ãç¦å³¶çã¸ã®è£å©éç³è«æéã¯ã移転å®äºæ¥ãã3ã¶æãçµéããæ¥ã®å±ããæã®æ«æ¥ãåãåããã¯è¢«ç½è
ã®æ®ããå建ç¸è«ãã¤ã¤ã«ã¾ã§ã
ã»å±±å½¢çã«é¿é£ããã¦ããä¸å¸¯ã®éç¨ä¿é²ä½å®
æ°è¦å
¥å±
è
ãåéãã¦ããã
ã質çå¿çã
Qåä¸ãä½å®
ã®ä¸å¸¯ä¸»ã¯å¤«ã§ããããå®éã¯ç¦å³¶ã§çæ´»ããã¦ããäºéçæ´»ã§ããããã®å ´åã®ç³è«ãåå
¥è¦ä»¶ã¯ã©ããªããã
Aããã¾ã§ãé¿é£ãã¦ãã人ã¸ã®æ¯æ´ã«ãªãã®ã§å
¥å±
ãã¦ãã人ãç³è«ãããã
Q夫ãå®å®¶ã§å¦»åãé¿é£ãã¦ããå ´åãäºéçæ´»ã®è¨¼æã¯å¯è½ãã
Aä½æ°ç¥¨ãä¸ç·ã ã¨ç¥ç¶æ¯ã®æå¾è¨¼ææ¸ãå¿
è¦ã«ãªããç¥ç¶æ¯ã¨çè¨ãå¥ãªãã°ãå
Œ
±æéã®æ¯æãã§è¨¼æã§ãããå
¬çã«è¨¼æã§ããæ¸é¡ãããã°ããã
Qéç½åã¯1æ¸å»ºã¦ã«5人ãå±
ä½ãã¦ããã妻å4人ã¯é¿é£ã夫ã¯å®å®¶ã«ããããç¾å¨ã¯éç½åã®å®¶ã«ä½ãã§ã¯ããªãã®ã§ãå
Œ
±æéã®æç´°ã¯åºããªãããã®å ´åã¯ã©ããã
Aä½æ°ç¥¨ãä¸ç·ã§ããå®å®¶ã®é»æ°æéãå¥ã§ããã°å¥ä¸å¸¯ã¨ã¿ãªãããã
Qç³è«æ¸ãç¡äºã«å±ãã¦ããã®ããç³è«ãã人ã¯ããããªãã®ã§ãåçããæ¨ãéç¥ãããã¨ã¯ãªãã®ãã
Aç¦å³¶çæ°è³çè£å©éäºåã»ã³ã¿ã¼ã¸ç¢ºèªãã¦ãããã°ããã«è¿äºãã§ãããä¸å®ãªæ¹ã¯é»è©±ã§ç¢ºèªããã¦ã»ããã
Qç¸è«ä»¶æ°ãåä»ç¶æ³ã¯ã©ããã
Aç¾å¨ã¯800件ãè¶
ãã¦ãããç¸è«å
容ã¯å¶åº¦ãæéãæ¸ãæ¹ãå¤ãã
Qæ¬ç³è«ã®ééããå¤ãã±ã¼ã¹ããè¨ç®ãã¹ã»æ¸é¡ãã¹ã®å ´åã¯ã©ã対å¦ãã¦ããã®ãã
Aæ¬äººã«é»è©±ã§ç¢ºèªããä¿®æ£ããã¦ããã
â 第2é¨ãæ´»åå ±åãç¾ç¶ã課é¡ã®å
±æ
ï¼æ´»åå ±åã»åç¥ï¼
ã»12æ15æ¥ã«ç³è«æ¸ã®æ¸ãæ¹ã®èª¬æä¼ãéå¬ããã
ã»11æ14æ¥ã«å±±å½¢çã»ç¦å³¶çã»æ°æ½çã»å®®åçã®ï¼çã®é¢ä¿è
ã§ç ä¿®ä¼ãéå¬ãç½å®³æã®é¿é£æã§ã®åªãã空éãå®å¿ãã¦éã¹ãå ´ä½ãã®ç ä¿®ã§ã平常æã»é«é½¢è
ã»é害è
ã«ã使ããå
容ã ã£ããåå è
ãå¤ãåé£çã¨ã®äº¤æµãã§ããã
ã»ãå¤ã飯ã®ä¼ãã¯3æã¾ã§ç¬¬1éææ¥ã«éå¬ãã¦ããã
ã»æ¥å¹´åº¦ã®ããµã£ããã®ç¶æè²»ã®ããã¯ã©ã¦ããã¡ã³ãã£ã³ã°ãæ°æ¥åããå§ããã
ã»ä»å¹´åº¦ã¯ããµããã¨ç¦å³¶äº¤æµäºæ¥ãã山形çã®ã¹ãã¬ã¹ã±ã¢äºæ¥ãã®2ã¤ã®äºæ¥ããã£ãã
ã»10æ1æ¥ã®ãã¢ããã»ã©ãã¼ãã¯é¿é£è
ããä¼ç»ããã¦ããããèªç«æ¯æ´ã¨ãã¦éå¬ããã100人åå¾ã®åå ããã£ããæ°ããªè©¦ã¿ã§å¤§å¤ã ã£ããã大æåã§ãã£ããç¦å³¶çã«å¸°ã£ãæ¹ãç¦å³¶ã®ã¤ãã³ãã§æ´»åãã¦ããã
ã»11æ17æ¥ã®å¤ã«ã天童å¸ç¤¾åã®ååã§ã女æ§ã®ããã®å¤ã®ç¸è«ä¼ããéå¬ãããåå è
ã¯å°ãªãã£ãããåå ãã¦è¯ãã£ãã¨è¨ã£ã¦ããããã
ã»10æ28æ¥ã«æ¯æ´è
ã¨é¿é£è
ã®éã«èµ·ãããããã¡ã³ã¿ã«ãã©ãã«ã®è¬åº§ãããã
ã»å±±å½¢åå°ã§ãããããã³ã³ãã®ã¤ããæ¹ãã®ãã¼ãã§è¬æ¼ãããã親åã300åãåå ã
ã»ä»å¾ã¯ååã»ç¦å³¶ã§ã®è¬åº§ã対話ã«ãã§ã®ã¤ãã³ãã決ã¾ã£ã¦ããã
ã»å¿ã®é²ç½ã§ããã¹ããä½æä¸ã大ããªç½å®³ã®æã«èµ·ãããã¡ã³ã¿ã«ãã©ãã«ã®äººéé¢ä¿ã®æªåã»ã³ãã¥ããã£ã®å´©å£ãªã©ã®å¯¾å¦æ³ããããã¹ãã«ã¾ã¨ãã¦ããã
ã»ãç³è«æ¸ã®æ¸ãæ¹è¬åº§ãã訪åã®éã«åºå ±ãã¦ããã
ã»ç±³æ²¢å¸é·ãç¦å³¶çåºã«è¡ã£ã¦ããã
ã»ç¸è«å¡ã®ç ä¿®ä¼ãä¼è°ãªã©ã11æã«éå¬ããã
ã»ä¸å±±ã§11æ19æ¥ãè¶ä¼ãéå¬ããã
ã»12æ10æ¥ã«æ±æ ¹ã®ã¿ã³ãã¯ã«ã»ã³ã¿ã¼ã§ç¸è«ä¼ãéå¬ããã
ã»11æ25æ¥ãæ¹æ´å®ã®ãåããã¨ãé¦ãè¢ä½ãããéå¬ãã好è©ã§ãã£ãã
ã»12æ5æ¥ååã¯ã社åã§åçµãåå¾ã¯ãæ°è³ã®è£å©éã®ç³è«ã®æ¸ãæ¹ãã®è¬åº§ãããã
ã»åç¸é¦¬å¸å°é«åºã®ãã©ã³ãã£ã¢æ´»åã»ã³ã¿ã¼ã«è¡ã£ã¦ããã110åè¿ãåå ã§é©ããããã¼ãºãããããããé¢æ±æ¹é¢ãããåå ãã¦ããã
ã»ä»å¹´ã¯ãããããããã¨ãã¤ãªãããããããã®éå¶ç®¡çããã¦ããã
ã»ç¦å³¶çã»å®®åçã»å±±å½¢çã®ä¸é«çã対象ã«ãã¦æ®æ®µã®çæ´»ãå°æ¥ã«å¯¾ããäºãå¦æ ¡ã«å¯¾ããä¸æºãªã©ãéç½å¾ã®åã©ãéã®æèã1700ååã¢ã³ã±ã¼ãã«ã¾ã¨ãããæ¯æ´ã®åèã«ãªãã¨æãã
ï¼é¿é£è
æ¯æ´ã®ç¾ç¶ã»èª²é¡ï¼
ã»11æ18æ¥ç¾å¨ã§å±±å½¢å¸å
ã®é¿é£è
æ°1,308人375ä¸å¸¯ã
ã»åãä¸ãä½å®
ããã¢ãã¼ãã«ç§»ãä¸å¸¯ã¯å¢ãã¦ããã
ã»çã®åãå
¥ã人æ°ã¯ãå
æãã36åæ¸ã2,969人ã§ããã¡ç¦å³¶çããã¯2,700人ã«ãªã£ãã
ã»åä¸ãä½å®
ã®éå»å±ãåºã人ãå¤ããªã£ã¦ãã¦ããããç¦å³¶çã«æ»ãä¸å¸¯ã¯å°ãªãã
ã»è£å©éã®åãåããã¯å¤ããªã£ã¦ããã
ã»æ»ã£ã人ã¸ã®æ¯æ´ã¯ããµããã¨ç¦å³¶ãã®äºæ¥ã§å£ä½ã«ãè£å©ã¯ãããç¦å³¶ã«å¸°éãã親åã¸ã®æ¯æ´ããã¦ããå£ä½ãããã
ã»é¿é£è
ã®ä»å¾ã®ä½å®
ã«ã¤ãã¦ã®æ°æã¡ãæ¥ã
å¤åãã¦ããã
ã»ããããç¦å³¶ã«å¸°ã人ã®ãµãã¼ãããã©ããããããã®ã課é¡ã«ãªã£ã¦ããã
ã»çæ´»å建ç¸è«æ ç¹ã®ã¨ãã¾ã¨ãããã¦ãããç¦å³¶çå
ã¨çå¤ãã©ãçµã¶ã®ãã¨ãã段éã«ãã¦ããã
ã»é¿é£è
ãããäºå確èªãããããç³è«æ¹æ³ãããããªãã¨è¨ããããä»å¾ããç³è«æ¸ã®æ¸ãæ¹è¬åº§ããéå¬ãã¦ã»ããã
ã»11æã«ãªã£ã¦æ¥å¹´åº¦ã®å¼è¶ãã決ã¾ã£ãä¸å¸¯ã2.3件ãã£ãã転å±
å
ãããããªãã
ã»æ¥å¹´åº¦ã®å°±å¦æ´å©ã¯ãã¾ã é£çµ¡ãããªãã
ã»é¿é£è
æ°ãå°ãªããªããã¼ãºãå¤æ§åãã¦ãã¦ãããç¦å³¶çã«ãã人ã¯é¿é£ããã¦ããæ¹ã®ç¶æ³ãããããªãããã£ã¨ã¤ãªãã£ã¦ãããã°ããã¨æãã